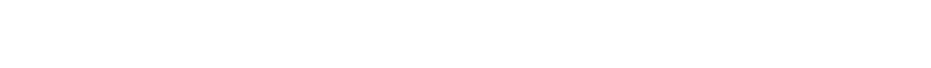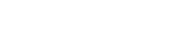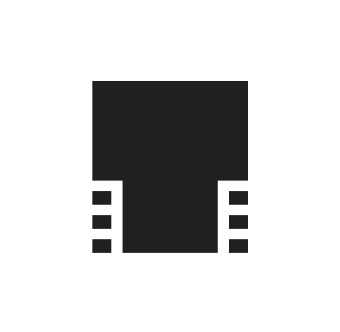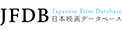東京国際映画祭公式インタビュー 2020年11月8日
『マリアの旅』
ダビッド・マルティン・デ・ロス・サントス (監督/脚本/エグゼクティブ・プロデューサー)

ベルギーで老後を送るスペイン人のマリアは、病室で相部屋になった若いベロニカと知り合い、人生の大きな転機を迎える──。短編やTVドキュメンタリーで数々の賞を受賞してきたスペインの才人、ダビッド・マルティン・デ・ロス・サントス監督の初長編作品。思いがけない出会いが、冴えない老後を過ごすマリアに生きる歓びを掻きたて、新たな目覚めをもたらす様を簡潔なタッチで綴っている。深い眼差しで、母親世代の女性の心の解放を見つめた監督に話を聞いた。
――お母様を看取る経験から作品を構想されたそうですね。
ダビッド・マルティン・デ・ロス・サントス監督(以下、サントス監督):母が病で末期にあると知ったことがきっかけですが、脚本を書くうちにどんどんストーリーが発展していき、老女と若い女性が懇意になるアイデアに落ち着きました。キャラクターを理想化すると物語が浅くなるため、深みを与えるために敢えて距離を置き、さまざまな調べ物を行いました。
――その結果、分かったことは?
サントス監督:母の世代はスペイン市民戦争後の、フランコ政権による独裁時代を長く生きてきました。フランコはカトリックの規律を国家化することを掲げ、良妻賢母を奨励して、性やエロティシズムという人間の根源的欲望をタブー視してきた。つまりこの世代の女性は、女性としてのアイデンティティを確立することが難しく、確立するために必要な性的探求を禁じられ、通過儀礼を経ることも許されていませんでした。
民主化後(取材者注 – スペインの民主化は1975年)に生まれた私にとって、これは驚くべき事実であり、マリアの内因的なモチーフとしました。
――年齢も性格も違うベロニカのキャラクターは、どう思い描いたのでしょう。
サントス監督:マリアは家族の中で占める位置や人間としての尊厳、誠実さをカトリックの堅固な価値観に準じていますが、ベロニカはポーランドの社会学者ジグムント・バウマンがいみじくも定義したように、「液状化」した現代を生きています。人間関係であれ仕事であれ、縛られることが怖い女性です。
母のファティマはフランス領だったマグレブの出身で、一切を裁ち切りたくてアルメリアへ移り住んだ人物であり、彼女も母と同じようにしてベルギーへやってきます。ベロニカには断絶を、マリアには継承を象徴させて、断たれた家系と受け継がれてきた価値観をバランス良く提示しながら、ふたりの関係を構築しました。
――ベロニカは母親の名前を日本語で入れ墨しています。
サントス監督:あれは連れ合いの姪が中東系でもないのに、祖母の名前をアラビア語で入れ墨していたことにヒントを得ました。今のスペインの若者は日本文化が好きで、特に意味はなくても格好いいと感じています。ベロニカも同じです。
――ベロニカが救命室にマリアを呼び、「人は動けなくなると時をゆっくり感じるものね」と言います。遺言のように響いて印象的でしたが。
サントス監督:このシーンは自信がなくて、実は何度も書き直しています。死は人にある種の超越性を与えますが、あまり超越的なセリフにしたくありませんでした。ベロニカは鎮痛剤を打たれて朦朧としており、幻覚を見ています。最初のセリフはもっと文学的でしたが、最終的にシンプルにしました。
――マリアは旅に出て、スペイン南部の港町アルメリアにやってきます。
サントス監督:アルメリアはヨーロッパ唯一の砂漠があり、楽園のような自然が広がっています。私の大好きな土地であることから、後半の舞台に選びました。この地方出身のベロニカに土地の訛りがないのは、先程触れたように母親が流れ者だったからで、対するマリアの故郷もダム建設で水没した北部の村にして、ふたりが故郷喪失者であるという設定にしました。
――食堂の主人ルカとベロニカの元恋人フアンとの出会いが、マリアに思いがけない転機を到来させます。
サントス監督:アルメリアに移った途端、強い陽射しや白い家並みが目に飛び込んできますが、私は人物についても風景があると信じていて、アルメリアの住人を風景のように描こうとしました。
ルカがルーマニア人で、ベロニカの生家に住む女性がキューバ人なのは、近年この地方に移民が増えている現実を反映しています。フアンに関しては土地を一歩も出たことがない、ずっと郷里にいて行き詰っている男性を思い描きました。
――旅を終えたマリアは家族に内緒で、自身に忠実に生きようと決意します。
サントス監督:マリアは母として、また妻としての役割に生涯縛られてきましたが、旅を終えて活力に満ちたまま帰途につきます。旅を通して自分を知り、知ったことで自由を手に入れます。ずっと家族の面倒を見てきた彼女は、人生の借金を返済し、自分を思いやることの大切さに気づくのです。
――旅の最後で結末とする選択肢もあったはずですが、映画はマリアのささやかな自己解放を描いて終わります。余韻に浸りながらも、ここまで描くのはさすがスペイン映画だなあと感心しました。
サントス監督:それはまたなぜ?(笑)
――ありきたりな意見になりますが、フラメンコと闘牛からイメージされる情熱の国、そしてカトリック信仰と対決した異端の映画作家、ルイス・ブニュエルを生んだ国だからです。
サントス監督:いろんなことがあって日常は変わらなくても、マリアは自らのアイデンティティに忠実に生きたいと希う。ありがちな結末にしないで、最後までマリアの内的なモチーフを探究した結果、このエンディングに至りました。