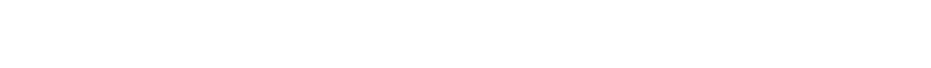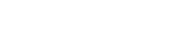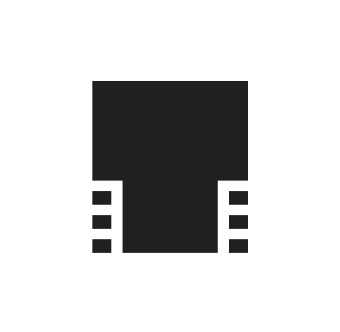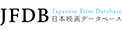吉田喜重監督、リティ・パン監督が語る戦争の記憶 映画作りに向き合う原点とは

吉田喜重監督とリティ・パン監督
第33回東京国際映画祭と国際交流基金アジアセンターによる共同トークイベント「「アジア交流ラウンジ」リティ・パン×吉田喜重」が11月8日、都内で開催され、吉田喜重監督がカンボジアのリティ・パン監督とオンラインで語り合った。
2003年、吉田監督が70歳の時に公開された映画『鏡の女たち』は、原爆がもたらす苦しみを、三世代の女性たちの目を通して描き出したドラマ。一方、第21回東京フィルメックス特別招待作品として上映されたパン監督の最新作『照射されたものたち』は、ナチスのホロコースト、カンボジアのポル・ポト政権下の虐殺、そして広島、長崎の原爆投下という人類史上3つの悲劇を大量の資料映像のモンタージュによって描き出したドキュメンタリー映画となる。
「わたしは『鏡の女たち』を映画監督として最後の作品と決めて作りました」と切り出した吉田監督は、「わたし自身は戦争中、福井県にいましたが、大空襲を受けて一家離散となりました。家族に会うまで2日かかりました。戦争の怖さ、恐ろしさは12歳の時から身につけています。したがって戦争反対ですし、平和こそが人間のあるべき姿だと今でも思っています。そういう記憶を鮮明に映画に残したいと思って映画を作りました」とその原点を明かす。「わたしは、映画監督になってよかったと思ってます。映画は自分が生きた時代をもっとも強く反映できるからです。わたしが今、映画を作る気力がないと言っているのは、もう既に生きている時代に興味がなくなったということも意味しているわけです。映画は生きているものです。それが映画の素晴らしさだと思っています。そういう映画を職業とできたことを誇りに思っています」と語る吉田監督。今年4月には初の小説作品「贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争」を刊行し、映画とは違う分野で、新たな表現に挑戦しているという。
一方のパン監督は「わたしは数年前から映画を作っていますが、もともとは小学校の先生になりたかった。わたしの国の歴史はとても複雑で難しいことがありました。戦争があり、虐殺が起こりました。その後はその記憶を語らないといけない、表現しないといけないと思うようになりました。そのための手段として映画を作ろうと思ったのです」と明かす。そして、「いつも映画を作るときは複数の理由がありますが、けれども映画を作る本当の意味はひとつだけなんです。映画は難しい題材を扱うことができます。虐殺や戦争、原爆などを扱う時に、その映画を作る仕事は大変デリケートになります。私としてはまさにこの映画を作る理由があるわけです。生き延びた人、生き残っている人が、自分が見たものを証言しない、言わないことに何の意味があるのでしょうか? 記憶を伝え、苦しみを乗り越えないと何の意味があるのでしょうか?」と訴えかける。
さらに、パン監督の両親がポル・ポト政権下の虐殺で亡くなったという話を聞いたという吉田監督が、自国民同志が殺し合うという悲惨な戦争について質問すると、パン監督は「わたしが興味があるのは、街角で行われているような目の前の暴力ではなく、”なぜ虐殺したのか”ということ。その意図に興味がありますし、重要だと思うのです。虐殺を説明することは誰にもできません。そこにはイデオロギーがあるだけですから。わたしが話しているのは、人類に対する犯罪、破壊行為について。これは言葉では説明ができませんが、それを理解しようとする道筋に興味があります。人間の大量破壊について理解しようとしています」と前置きを入れる。「外から見ると(ポル・ポト政権の)クメール・ルージュが人々を殺したわけですが、わたしはカンボジア人がカンボジア人を殺したとは考えていません。わたしの両親も人を殺したことはありませんから。わたしは極度の暴力が起きる理由をイデオロギーの角度から探ろうとしているのです」と返答。「これを理解しようとしなければ、悲劇を繰り返すことになってしまう。アーティストにはそうした責任があると言った方がいいでしょうか。もちろんわたし自身、軽い映画を作りたいですよ。ミュージカルやコメディなどを作りたい。映画にはそういう機能もありますから。わたしもいつか娯楽映画を作る日が来るのかもしれません。でもわたしの人生は1回限りですから、まずはわたしの国の歴史を語ることから始めたというわけです。ある日、自分自身の喜びのためだけで軽い映画を作ることがあるかもしれませんけどね」と笑ってみせる。
パン監督の最新作『照射されたものたち』は、ナチスのホロコースト、カンボジアのポル・ポト政権下の虐殺、そして広島、長崎の原爆投下など、目を背けたくなるような資料映像が使用されている。そのことについてパン監督は「恐ろしいことがひとつあります。原爆を見て美しいと思ってしまうということです。それは原爆だけでなく、爆撃するものすべてがそう。それはゾッとすることです。一方、ひどい扱いをされている死体を見ると、その時の暴力性がどんなものか分かります。わたしはこのような映像をつなぎ合わせました。わたしは平和の中に生きたいですし、平和のために生きることが重要です。それならば平和のためには、この堪えがたい映像を見るべきだとわたしは思うのです」と力強く語る。「今、情報は早く流れて、若者たちは現実を見なくなっています。この映画には死体がたくさん出てきます。死体の映像だけで音がありません。おそらくそういうものを見た人は、この映像のことを思い出すでしょう。映画は世界を変えることはできません。映画は映画であり、それ以上のものではないからです。しかし人を少しだけ助けることはできるんじゃないかと思っているんです。自分の目の前で不正義が行われた時、それに反対をしなければならない。立ち上がって反対をとなえるべきだと。そういう風に映画が背中を押すことはできるんじゃないかと思うんです」と訴えかける。
「大変答えにくいご自身の過去について語っていただきました。(小説「失われた時を求めて」の)プルーストの場合は楽しい思い出でしたが、悲しい記憶もあるんだということを今、あらためて思い知らされました。申し訳ありませんでした」とおもんばかった吉田監督に対して、パン監督は「大丈夫です。言葉で語ることは重要なことだと思うのです。言葉によって歴史を普遍的なものにできるからです。わたしは語ることに決めたんです。もし言いたくなかったら何も発言しないと思いますよ」とほほ笑んでみせた。
新着ニュース