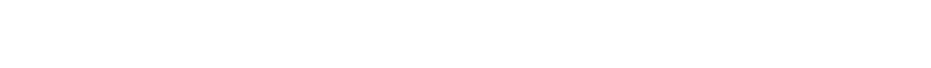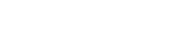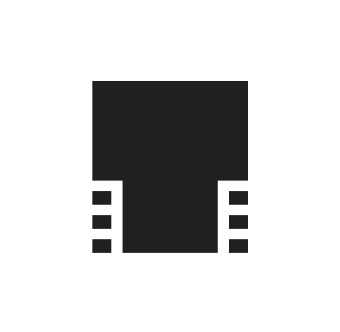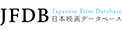東京国際映画祭公式インタビュー 2020年11月8日
『赦し』
ジェム・オザイ(監督/脚本/編集)

トルコの山村で、厳格な父親イムランと無口な母親アシエと暮らすアジズとメリクは、正反対の性格の兄弟。活発で父に可愛がられているメリクに、内向的な兄アジズはどことなく嫉妬心を抱いている。ある日、彼らは父から銃の扱い方を習っている最中、アジズが誤ってメリクに向けて発砲してしまい…。セリフをほとんど使わず、表情の芝居と圧巻の美しい景観でものを語る叙情的なドラマが本作。監督のジェム・オザイは、本作で長編監督デビューを果たした。
――このテーマを選ばれたきっかけはなんでしょう?
ジェム・オザイ監督(以下、オザイ監督):このストーリーの着想もとは実話なんです。私はトルコの映画業界で20年ほどプロデューサーなどを務め、映画やテレビドラマを手がけてきました。そのキャリアの中である映画のプリプロダクションの際、とある田舎町に行った時のことです。警察の職員に協力を仰ぎ、彼の家に行き彼のふたりの子どもに会いました。彼はとても頑固で厳しい人で、子どもたちに対してとても不公平な態度を取っていたんです。
そのロケハンの後、彼と仕事をすることになったのですが、急に連絡が取れなくなりました。彼の隣人に事情を聞いてみると、なんと長男が次男を撃ち殺してしまった、と。それを聞いてとてもショックを受けました。ただ、よくよく考えてみると、彼の異常な厳しさが伏線だったのかとも思ったんですね。
――本当に起こりうる設定とストーリーだとは思いましたが、まさかそこまで監督に近いところで起きていたとは。
オザイ監督:そうなんです。それで、彼と彼の家族の関係はいったいどうなってしまったんだろうという疑問が常につきまとっていたんです。それが本作の製作へと導くことになりました。
――それだけの大事件ですが報道はされたんですか?
オザイ監督:この手の事件はトルコではしばしば起きるんですよ。ですので報道されませんでした。例えば、新聞だったら1面ではなく3面記事程度。地方の方では自然と共生しているために、猟銃を持つことは当たり前なんですね。もちろん認可制で正式なライセンスがあることが条件ですが、どこの家にもあるものだと思っていただいていいです。
――この重いテーマを長編の監督に初挑戦するにあたって、感情的なセリフを廃して作ることを決めた理由は?
オザイ監督:この物語において、役者が語りすぎると、逆に何かが足りなくなってしまいます。彼らの心理的な部分とコネクトするためには、セリフを削るほうが得策だと思ったんです。実は、対話のシーンが多くあるバージョンも試してみたんですが、感情的、精神的な部分を映し出すことができませんでした。それで、思い切ってセリフを最小限にしたんです。
――英断ですね。
オザイ監督:この事件が実際に自分の身の回りで起きたことを考えれば、むしろ饒舌に話すことはあまりないんですよね。それに、子役のふたりは演技経験がなかったので、セリフを用意するのが本当に大変で。話をさせることで作品の中にある感情的なものから遠ざかってしまうと思ったんです。
母親アシエにも話をさせるつもりでしたが、映画じゃなくてドラマっぽくなってしまいます。こういう題材だからこそ、映像の文法で人間性、関係性を描き出すことができるはずだという信念があったので、セリフを最小限にするのは命題でした。
――父親役の方は俳優ですよね?
オザイ監督:父親役のティムル・アジャルと母親役のエミネ・メルイェムはプロの役者です。ティムルは人気のある役者で主にコメディの舞台に立ってます。今までこういったシリアスなドラマに出たことはないので、彼のキャリアにおいて本作は今までとは異なる部類の作品となりました。
エミネはトルコ人ですがフランス在住で、プロの役者として映画や短編映画に出ています。
――コメディアンがセリフを封じられるとは、アジャルさんには挑戦でしたね。
オザイ監督:その通りですね。しかも子役がアマチュアですから。
――画作りの美しさが印象的ですがどのようなプロセスを?
オザイ監督:芸術監督の作り出す雰囲気を重視したのが本作のアプローチです。ロケ地は撮影監督のセバスティアン・ウェーバーが探してきた場所で、作品にピッタリだったんですが。人里離れた泊まるところもない場所だったので準備には苦労しました。
――長編処女作となると資金やスケジュールで厳しかったのでは?
オザイ監督:企画から完成まで4年以上かかりました。実は、トルコにはインディペンデント映画を支援する組織があまりなく、文化観光省映画総局の支援プログラムがメジャーです。本作はその審査に通ったことで実現しました。でも、この審査は初回の提出では絶対に通らないことで有名で、私も2度目の申請で合格したんです。
その後、アンタルヤ国際映画祭の企画開発プラットフォームで、TRT(トルコ・ラジオ・テレビ協会)の賞を受賞したことをきっかけに、TRTと共同プロデュースすることができたんです。面倒なことは多かったんですが、初長編で支援を受けられたのはラッキーでした。
――多くのサポートを受けられたことは、トルコの若い映画人に勇気を与えましたね。
オザイ監督:もちろん。その人たちに必要なことはまず決心すること。そして、やりきる頑固さ。私は映画芸術とは“解決を見つける芸術”として考えられると思っています。トルコ国内での映画制作に携わっている人たちは、その道を見つけ出すべきですね。