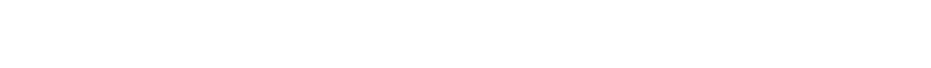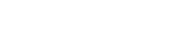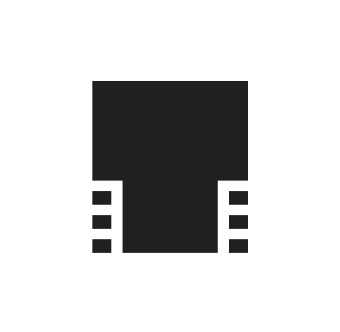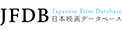11/4(水)日本映画クラシックス『無法松の一生』の上映後、Q&Aが行われ、宮島正弘(監修)、山崎エマ監督、エリック・ニアリさん(プロデューサー)、 五影雅和さん(エグゼクティブ・プロデューサー)が登壇しました。
⇒作品詳細
田中文人(以下、司会):第33回東京国際映画祭 日本映画クラシックス部門『無法松の一生』そして『ウィール・オブ・フェイト~映画『無法松の一生』をめぐる数奇な運命~』の上映にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。東京国際映画祭、田中文人と申します。よろしくお願いいたします。英語通訳は鈴木小百合さんです。
それではゲストの方を早速お招きしたいと思います。『ウィール・オブ・フェイト』の監督の山崎エマさん、そしてプロデューサーのエリック・ニアリさん、そしてエグゼクティブ・プロデューサーの五影雅和さんです。そして『無法松の一生』の修復の監修をなさいました、そして宮川一夫カメラマンの助手も務められました宮島正弘さんです。早速ですが、宮島さん、今日、客席でご覧になっていましたけれども、まず改めて感想を一言いただけますでしょうか?
宮島正弘さん(以下、宮島さん):今日はどうもありがとう。今日僕も初めて観ました。実を言うとこれはニューヨーク、ポルトガルで修復していたものです。だからコロナのおかげで現場にいることは出来ませんでした。電話とか言葉でしか話せなかったんですけど、やっと観られて…。何せ77年前のフィルムで、非常に悪い状態でした。悪くて大変だったけど、皆さんに観てもらってどう思われたかわかりませんけど、精一杯やってもらいました。
司会:そして『無法松の一生』という作品をきちんと理解するためには、この作品がとても魅力があったからではないかと思います。『ウィール・オブ・フェイト』を監督されました山崎エマ監督です。
山崎エマ監督(以下、監督):本日はありがとうございます。山崎エマです。今回『無法松の一生』が修復されると聞いたときに、隣にいる夫のエリックが、KADOKAWAの五影さんとか宮島さんと一緒にしてきたことを横で見てきたことがありまして、ずっと何年も前から宮島さんが「『無法松の一生』だけは死ぬまでに修復しないといけないんだ」と言っているのを聞いていたので、そういうことが実現出来た時には、そういう瞬間に立ち会ってドキュメントしたいと思いました。さらに、戦争中、映画が作られた背景を調べていくと、あらゆる資料をかき集めて、なるべく本人たちの言葉を集めて、そこから凝縮したものをドキュメンタリーに入れました。例えば今、コロナ禍の中で、コロナじゃない話を撮るのがどれだけ大変かということを感じながら、当時、戦争の真っ只中にこのような人間味溢れるものを、戦争中という気配を感じさせずに作り上げた強い信念、さらにはいろいろな権力に立ち向かうというか、上手くすり抜けて作り上げたという制作者、映画界の先輩たちの想いを今回、4K修復した本編と同時に、今後、日本だけじゃなくて世界中に届けられる場を作った方が絶対に喜ぶんじゃないかな、と。本編と併せてそういうことを知ってもらった方がこの作品は今、そして今後生きるんじゃないかと思ってドキュメンタリーを作らせてもらいました。そして今日は実はドキュメンタリーの制作にあたってお世話になったいろいろな方々が来ていて、出演者の方々も来ているのでご紹介させていただきます。私的には今日、稲垣監督の息子さん、宮川カメラマンの息子さん、そして主演・阪東妻三郎の息子さん、この3人が同じ場所に集まったっていうことはすごい素晴らしいと思っていて、もしよければお立ちになっていただけますか? 稲垣涌三さんと宮川一郎さんと、そして田村 亮さんです。ありがとうございます。そしてさらにもう1組だけ。今回アニメーションを作りました。やっぱり77年前の色々なストーリーが文章でしか残っていない中で、どう表現するべきかと考えたときにアニメーションに辿り着いて。その際、まさかこんなアニメーション界の巨匠の方とご一緒出来るとは思っていなかったんですけれども、今回、古川タクさん、「ゴリラ」という制作チームの皆さんとやらせていただきました。どうぞお立ちください。
司会:それではプロデューサー、監督のご主人でもあるエリックさん、一言お願いいたします。
エリック・ニアリさん:皆さんこんにちは。今日は来ていただいて本当にありがとうございます。数年前からKADOKAWAさん、マーティン・スコセッシ監督のフィルム・ファウンデーションといろいろな日本の名作を修復出来るようになりまして、それによって宮島さん、それから宮川家、宮川一郎さんをはじめ、宮川一夫関係のいろいろな方と深い付き合いが出来ていて、この作品は本当に宮川家、宮島さんにとってとても大事な作品で、2年前から企画してきたんですが、やっとこのつらい2020年、やっとこのプロジェクトを実現出来て非常に嬉しいです。皆さん、ありがとうございました。
五影雅和さん:本日はお運びいただきまして誠にありがとうございます。また本作品をこのような場所で上映していただきました東京国際映画祭の皆さまにもお礼申し上げます。皆さんお話されていて、ちょっと重複する部分はあると思うんですけれども、これまでにも4K修復だったりとかこのチームでやらせていただいております。いつも決まった作品を宮島さんに「今回これをやるんで修復をお願いします」というところでスタートしてたんですけれども、本作品に関しては宮島さんが「これは俺が死ぬまでにどうしてもやりたいんや」というところがあって、今のお披露目に至っております。本当に宮島さんに引っ張られる形で、そしてここにいるスタッフ、メンバーがいなければ実現しなかったと思っております。またドキュメンタリーにご出演いただいた方、フィルム・ファウンデーション他、本修復、本ドキュメンタリーに協力いただいた方に厚く御礼申し上げます。
実は上映の順番というところで、今回ドキュメンタリーを先に観ていただいて、そのあとに本編をご覧いただきました。実はエマさんとかとも話していて、まずドキュメンタリーを観ていただくということが果たして良いのかどうか、もしかして初めて観る方にとって先入観を抱かせるということが良いのか悪いのか、というところが実は議論としてありました。でもその時も何となくと言ったらあれですが、観ていただき、深く理解するためにはそっちの方が良いんじゃないの、というところだったんですけれども、今日ここに至るまでに自分の中でもいろいろと考えて、やはりこの作品が戦後75年というタイミングの今年に修復されたということを考えて、いろいろなメッセージを持っている作品でございますので、ある種この作品の持っている宿命として、いろいろなものを伝える手段として、もちろんエンターテインメント、一つの映画としても楽しんでいただけるんですけれども、いろいろなメッセージというものをこの作品を通じて感じてもらえるように、そういった想いで作っていただきましたし、これからも上映していければと思っております。副題にある”数奇な運命“っていうところではあるんですけれども、結局それをもたらしたっていうのは、戦争以外の何物でもなく、戦争がなければカットされることもなかったし、戦争がなければ広島、長崎で原爆が落ちなくて、園井恵子さん他、桜隊の皆さんが死ぬことはなかった……。これは『無法松の一生』のみならず、いろいろな作品でこういったことが起こっていると思いますので、もしこの作品、このドキュメンタリーを観て何か感じていただければ、さらに、さらに深く知って、心底から僕はこの作品を通じて「戦争はホンマにいやや」と思えるようになりましたので、ぜひ皆さんにもそういった気持ちになってさらに勉強していただければと思います。よろしくお願いいたします。
司会:今年の日本映画クラシックスは山中貞雄監督が3作品、そして稲垣 浩監督の作品をお送りすることができたんですが、まさしく五影さんが今おっしゃったように、山中貞雄は皆さんご存じだと思いますけれども戦地で亡くなっています。そしてこの作品『無法松の一生』も戦争に非常に翻弄された作品であります。ではありながらも、こうして今我々はこの作品を観て作り手たちのことを思い起こすことができるわけですね。とてもいい機会を今年は持てたんじゃないかと思っております。
私から宮島さんに一つ質問をしてもよろしいでしょうか。初めて出会われた時の宮川さんのご印象と仕事場での宮川和夫カメラマンはどんな方だったでしょうか。
宮島さん:僕は恋焦がれて宮川さんとともに仕事をしたいという一心で入ったものですから、もう神様と一緒に仕事をしているような感じでね、だけど好々爺、いいお爺ちゃんです。えええーっと言うように。その代わり、怒り出したらかー坊という、宮川一夫という名前でかー坊と、一時間でも二時間でも怒っているという人でした。けど、普段はにこにこにこにこして、僕達入った者は名前なんか呼んでもらえません。ぼん、関西では、ぼんおいで、ぼんやってみ、こういう、やっと名前を呼ばれたら、仕事ができるようになったら、名前を呼ばれるっていう感じでしたよね。
Q:ありがとうございます。監督の園井恵子さんへの想いというのを伺えればと思います。
監督:ありがとうございます。私も本当にこの今回の機会まで、園井恵子さんという方を全然知らなくて、ただやっぱりリサーチを続けると、唯一宝塚以外の映画がこれ(『無法松の一生』)で、本当にその後原爆で亡くなられて、当時は国民的女優になられて、彼女の写真を持って兵隊さん達が戦場に行った方々が多かったと聞いています。彼女の故郷である岩手のすごく田舎の方まで行かせていただいて、そこにいらっしゃる、彼女のことを語り継ごうっていう動きがすごくあって。それはやっぱりあんな小さな町から、本当にすごく昔、100年もかかってないかな、80年ぐらい前に、宝塚まで出て来て、夢を持って出てきた彼女のことを後世に伝えたいという方々の思いにすごい心を打たれて。今だと簡単なことも当時は難しい中で、そういう経験を積まれた方がこの役のために生きて、亡くなられたんじゃないかって言われるぐらい、ぴったりな役になっているっていうのは、このあらゆる運命、五影さんの話もありましたけど、彼女の悲劇的な、でもわかっているからこそ、たぶん今この映画を見ると、さらに儚く見えたりとか、彼女の存在感、特に当時一番の大スターだった阪妻さんの相手役としても、全然遜色なく、一度お会いしてみたかったなというのは取材していて思いました。