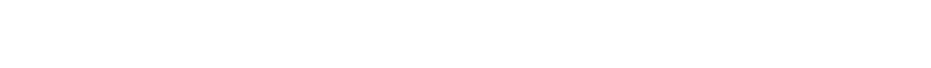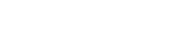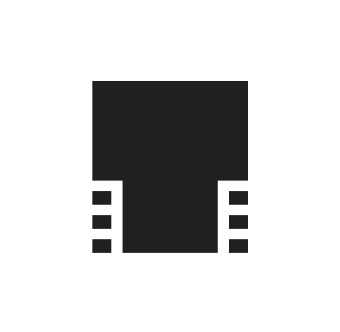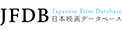11/3(火・祝)ワールド・フォーカス『海辺の彼女たち』が上映後、Q&Aが行われ、藤元明緒監督、岸 建太朗さん(撮影監督)、ディン・ダーさん(俳優)が登壇しました。
⇒作品詳細
矢田部吉彦SP(以下、矢田部SP):只今よりゲストの皆さんをお迎えいたしまして、Q&Aを行って参りたいと思います。私、矢田部と申します。映画祭の作品選定に携わっております。今日は先ほどご案内いたしました通り、日本語でのQ&Aを行って参りたいと思います。それでは、大変お待たせをいたしました。皆さま、どうぞ大きな拍手でお迎えください。『海辺の彼女たち』、藤元明緒監督、撮影監督の岸 建太朗さん、そして出演、ディン・ダーさんです、どうぞ。
ありがとうございます。皆さんようこそ東京国際映画祭へいらっしゃいました。また再びお迎え出来て、監督、光栄でございます。どうぞお座りください。よろしくお願いします。まずは皆さまに一言ずつご挨拶のお言葉を頂戴したいと思います。藤元監督からお願いいたします。
藤元明緒監督(以下、監督):監督と脚本、編集を務めました藤元明緒と申します。本日は本当にありがとうございます。
ディン・ダーさん(以下、ダーさん):ブローカー役のダーです。本日はお越しいただきありがとうございます。
矢田部PD:ありがとうございます。ダーさん、昨日青森から車で駆け付けてくださったということでありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして撮影監督を務めていらっしゃる岸 建太朗さん、お願いいたします。
岸 建太朗さん(以下、岸さん):『海辺の彼女たち』ご覧いただきまして本当にありがとうございます。撮影監督を務めさせていただきました岸 建太朗と申します。本日はよろしくお願いします。
矢田部SP:監督、彼女たちとの出会いと言いますか、ベトナムで沢山オーディションされた中で選ばれた3人ということなんですけれども、彼女たちの出会ったときの印象、そしてキャスティングした理由などをお聞かせいただけますか?
監督:僕とカメラマンの岸さんと、プロデューサーの渡辺さんと3人で去年の6月にベトナムに渡航して、大体100名ぐらいの方をハノイとホーチミンで3日間くらいオーディションをさせてもらいました。僕自身、オーディションをするっていうのが初めてでして、結構手探りでやりながら、本当にその人のパーソナルな、どういったバックボーンを持っているのか、というのをまず重点的に話を聞きながらオーディションをしていった、という形ですね。その中でこの3人の持っているバックボーンっていうのがこの映画にかなり近いというか、すごく感覚的に近いな、っていうのと、あと即興的な芝居とか、そういうことも出来る人たちだな、っていう判断で選んでいきましたね。
矢田部SP:なるほど。岸さんはカメラマンの目としてオーディションの時どういうところをご覧になりますか?
岸さん:当然海外でオーディションを行うっていうのも初めての経験でしたし、オーディションのやり方や体制も少し日本のものとは違って、僕らを本当に歓迎してくれて、向こうのプロダクションの方々が。何か映画のポスターみたいなのが下がっていて、オーディションのことをキャスティングコールっていうんですけど、キャスティングコールが始まります、みたいなかんじで僕らを受け入れてくれて、来てくれた方々も、簡単なプロットだけを送ったんですけど、すごく興味が、当然日本に技能実習生として来たことがある一般の方とか、俳優のキャリアがある方が沢山いる中で、今回の3人が、何て言うんですかね、これは藤元監督がよく言うんですけど、僕はフォンさんって主演の子が来たときに、それまでは(カメラを)ずっと三脚に置いていたのが、外して撮ったんです、無意識のうちに。
監督:何か顔の横で急に、喋ってるのに撮り出して。何か盛り上がってるってことはいいんじゃないか、みたいな。
岸さん:何か僕のそういう動物的な感性が動いた人が割と結果的に選ばれているところがありまして、それを色々な信頼関係の中で、藤元監督とも長年やってきたので。そういうところも含めて、直観も含めながら、バランスも含めて、会議をして決めていくようなかんじです。
監督:3人なんで、1人が良くてもダメなんですよ。この子いいな、って思っても。例えば見た目で言うと身長であったり。3人揃って且つ1人も良い、みたいな。パズルゲームみたいな。その中でも奇跡的に3人っていうのがはまったんですよね。
矢田部SP:なるほど。そしてダーさんとのご縁を語っていただけますでしょうか?どのようにしてチームに加わったのでしょうか?
監督:撮影準備中に青森の外ヶ浜っていうところで撮影させてもらったんですけど、青森で撮りますって決まって脚本にブローカーの男性役ってのがあるのでどうしようか、と。もちろん日本に住んでいるベトナムのプロの俳優の方っていないし、日本語が話せて現地に根付いている人っていうのがいないのかなと思い、料亭とかそういうツテを辿って紹介してもらったのがダーさんですね。さっき聞いたら、そもそも通訳で呼ばれてたって聞いて僕ちょっと初耳だったんですけど。それでロケハンに僕らが青森に行った時に、駐車場に来てもらって、早速ちょっと撮ってみよう、みたいな感じでした。撮って、カメラを覗いてみて、すごい説得力あるなと思って。そこの第一印象で決まりましたね。ダーさんにお願いしようと思って。
矢田部PD:ダーさん、映画出演は初めてということで。
ダーさん:今回、全くすべてが初体験で。
矢田部PD:ちょっとご感想をお伺い出来ますか?
ダー:最初は、出演して、って言われたんですけど、あんまり自信がなくて。僕、全く経験がないから、役を演じられるかな、と思ってたんですけど。すべてが初体験で色々な場面も、今まで見られない部分もあったので、色々な体験をさせていただきました。
監督:出演だけじゃなくて、撮影のお手伝いとか、休日、役者さんたちを気分転換に連れて行ってあげてくれたりとか、結構本当に現場をフォローしてもらって助かりました。
Q:監督にお聞きしたいんですけど、ベトナムの飢餓問題とかも度々聞いていて。全然知らないんですけど、ああいうことは実際に、飢餓、貧困の問題で、身分証を偽装してまで診断を受けなきゃいけない、切実な現実とか、ああいうのは実際にあるんでしょうか?
監督:ありがとうございます。元々この企画っていうか映画を撮りたいと思ったのが、実際に、日本に来ている技能実習生の方から、「僕が不当な扱いを受けていて、職を逃げたい」っていう相談を受けたところから始まっていて。そのことがあってからずっとこういったテーマや主題のことはずっと調べていて、実際にこういう妊娠の問題とか偽造IDのこととかっていうのは、本当に日常茶飯事とは言わないんですけど、ベトナム以外にも色んな国の人があって、そうした人たちを取材しながら脚本を作っていった、っていうのが今回の特徴ですね、脚本的に。僕の頭の中で組み立てたりするっていうのは最初の頃はあまりしなかったです。実際にどういうことが起きているか、っていうのを調べて、その中でフィクションとしてどういったリアルが描けるっていうのはすごく考えながら、僕とかプロデューサーの人とかで作って行ったってかんじですね。
矢田部SP:今、ケン・ローチ、(ルキノ・)ヴィスコンティっていう名前が出ましたけれども、藤元さんはそういった社会派リアリズムの監督を好んでいらっしゃるっていうのはあるんですか?
監督:そうですね。僕自身はそういうのも好きですし、何でも好きって形で、映画であれば。大作から社会派的なものまで好きです。ただ自分が撮るってなった時にどうしてもこの現実の中で僕らが映画を通して時代であったり人であったり社会であったりをどう見るかっていうのはやっぱりフィルモグラフィーとして残していきながら進んで行きたいな、ってういうのはすごく思っているので。
Q:映画の中のロケ地は対照的な寒々とした青森の土地で、きっと色々なご縁があってあそこで撮るってことになったと思うんですが、あの季節に、あの寒々とした、そして海というか、ああいうロケ地を選んだ経緯だとか、そこにどういうお考えがあったのかというのをお聞かせ願えますでしょうか?
監督:ありがとうございます。最初撮る前から、海があって、そこに雪が積もっているっていう条件の中でテーマとしてロケーションの、撮影場所を選びました。それも結構やっぱり外国の方とかと接していく中で、雪っていうのがすごく大きな印象としてあるなと思ったので。ベトナムって雪も降らないし、ああいう田園のところもあれば、都市部のところももちろんあるんですけれども、そことのギャップの中で彼女たちがどう生きてるか、っていうのを、今おっしゃった通り、狙いとしてはやっていましたね。ただそれも雪が積もって海があるっていうのは北海道か青森しかなくて…連日積もっているっていうところは。それで結果的に青森に偶然素晴らしい場所があったので、そこで撮影させてもらったっていう形です。
矢田部SP:ただ思ったよりも雪が少なかったということをこの前おっしゃっていましたね。
監督:この前も言ったんですけど、40~50年ぶりの雪がない青森だったんですよね。現地の人もびっくりしていて。これだったら東京で撮れるんじゃないか、みたいな。着いたときに何もなくて。撮影が始まる前日の夜から3日間くらい大降りになったんですね。それが本当に一番の大降りで、そこから残った雪を何とかかき集めて、1mくらいになっていった、って形ですね。青森って普段は腰まで行っちゃうんですけど、結果的に足首くらいまでしか積もっていなかったので、ああいう線路を歩く長回しのショットであったりとか、ああいうのは結構撮りやすいというか、上手くはまったなという感じでしたね。
矢田部SP:雪の少なさがむしろ寒々しさを強調しているような気も受けました。
監督:そうですね、結果オーライというか。
Q:カメラマンの岸さんは、ほぼ手持ちで撮影をなさっていたんですけれども、過酷な環境の中で、たぶん普段はあまり知らないような世界の問題をテーマにした中で、どういうことを考えてカメラを回していたのかを教えてほしいです。そしてダーさんは、普段、映画から見ても必ずこの方は技能実習生ではなくて、ふくよかな、ちゃんとした生活を持っている在日の方なんだろうなと思って見ていて、ダーさんは普段とは全く違うこの世界のブローカーという役を演じて、どんなことを考えていたのかなというのをお聞きしたいです。最後に監督なんですけれども、ずっと監督は前作から『僕の帰る場所』(18)から、日本にいる他者、多国籍の方で日本にいる様々なアイデンティティの方を追い続けて、今日の作品もそうなんですけれども、次作はネタバレをしない程度に、また引き続き日本にいる多アイデンティティを追い求めていくのか、それともまた新しい何かに挑戦するのかを教えていただけたらと思います。長くなってしまってすみません。
岸さん:前提として、当然ですけど、撮影者として映画に関わる時に、監督が描きたいと思った、例えば初期衝動であったり、その理由や個性というのを含めて、どういう作品を創るかというディスカッションの中で、僕がすごく印象に残ってたのが、当然日本にたくさんの外国の方がいらっしゃって、過酷な生活をしている方の情報も知っていますし、友人もいるんですけれども。藤元監督がおっしゃっていたように、労働があまりにも過酷だから逃げ出してしまって、そこでこの脚本ように、自らお腹にいる生命の命を絶ってしまうような方が、それなりに実際にいらっしゃるということとか、様々な話し合いの中で、それは例えば生命だったら目に見えないものですけれども、そういう目に見えない、生まれなかった命に対しての尊厳というか、ちょっと変な話ですけれども、ということを監督がこの映画を通してやりたいという思いが、僕はすごくそれを受け取っていて。常にそのことはイメージしながら撮りました。だから、彼女たちを撮っているんですけれども、フレームの外に広がる現実の世界との接地面としての映画というのが映画芸術の社会的な役割だと僕は思っているので、そこが透けて見えるようなもの、それは本当に簡単なことではないと思うんですけれども、自分が入り口、窓でありたいなというのがあったので、そこは自我を滅してというか真摯に取り組む、本当に話し合って決まったことを一個一個真面目に撮っていくだけなんですけれども、そこを一番意識しましたね。それは本当にみんなに支えられながら、いろんな人のサポートを受けながら一個一個ミッションを成功していけたので、そこが一つの映画の力になったのかなと思います。
ダーさん:僕の方は、映画の中でも“ブローカー”役なんですけれども、外でもブローカーとしてやっておりまして、一応建機とか建設機械とか、農業機械、そういうのをブローカーとして買い取ったり売ったりしていて。
矢田部SP:なるほど、今一瞬皆さん、びくっとしたと思うんですけれども(笑)大丈夫ですね。
ダーさん:研修員も雇っているんですけれども、何が違うっていうと、映画の中は人に仕事の紹介をしているんですけれども、そこだけが違うんですけど、あとはほとんど映画と変わらないですね。映画の役としてはすごいフィットしていたのかなと思いました。
矢田部SP:ダーさん、すごくリアクションが取りにくいんですけれども(笑)。実際の仕事がある意味役に立ったということですよね。ありがとうございます。そして監督、将来像と言いますか。
監督:将来像と言うか、この映画を撮るきっかけというのは先ほども話したんですけれども、もう一つすごく大きな点があって。僕にとって遠い世界というのは映画としてはあまりやってこなかった、いつも身近な生活の中で描いているつもりで。というのも、2,3年前に技能実習生の方が妊娠してしまって、中絶をするのか、はたまた帰国するのかという選択肢に揺れている女性というのが沢山出てきたんですね。そのすごく大きなニュースを見た時に、僕も外国人の妻がいて、その時ちょうど妊娠していまして、僕の奥さんは技能実習生ではないんですけれども、一つ制度であったりルールとか、来年には変わってしまうかもしれないし、何かのルールが変わったときに、僕の家族とかももしかしたら窮地に立たされるのかなとか、何か身近に恐怖が迫ってきたというか、そこの恐怖感が結構原動力で、映画にしなきゃなというのがあったんですね。そういったふうに、他者を描くというよりは、何か自分の中で出会ったりした人とか、思いとかを日々吸収していって、そこで僕は映画を創っているのかなっていうのは最近思っていて。なので、外国人だけをテーマにするというのは特に今後的な考えではなくて。もちろんそういった題材というのはやるかもしれないし、また全然違う、日本人だけの映画というのも創ろうと思っているし、そこはあまり決め込みすぎず、出会ったものに素直に反応していこうかなというのは考えています。
矢田部SP:なるほど。ありがとうございます。
Q:監督に質問です。技能実習の出身国というか、あらゆる国が現実としてはある中で、巡り合わせもあるかと思うんですけども、最終的にベトナムに決定した理由などあればお聞かせいただきたいです。
監督:ありがとうございます。元々はどこの国にするかっていうのは決まらずにプロットが進んでたんですよ。プロットっていうか、物語の軸と言いますか、流れっていうのは書き始めていて。前はミャンマーで撮ったんですけど、ミャンマー以外でちょっとやってみようっていう思いもありまして、ミャンマー以外の東南アジアの国っていう枠がありました、最初。その中でまず女優さんとか、テーマを選んで行こうとは思いつつ、その反面、特にベトナムの方っていうのは今多くて。何が多いかっていうと出て行った先のコミュニティと言いますか、ダーさんのような人がいたりする、というのがかなりベトナムの場合はリアリティがあるっていうのがあって、他の国でそれがない国もあったりするので、そことの、その事実関係とのバランスであったり。ベトナムで本当に素晴らしい3人がいたので、これは、僕もすごい何回も何回もベトナムに足を運んだ人間ではないですけど、何か、そこまで国の縛りっていうか、そういうのはあんまり意識はしなかったですね。どこの国の方とやってもそれは、それなりのものは僕はやろうと思ったし。特定の国っていうよりは、普遍的な国とか国の国境を越えたような何か物語を作れないかなっていうのはすごい意識してました。本当にそういう巡り合わせとか色んなことでベトナムに決まっていきましたね。大丈夫ですかね。
矢田部SP:ありがとうございます。すみません。ちょっと時間が来てしまいましたので、申し訳ございません。最後に、と言いますか、監督からひとつご紹介があるということでお願いします。
監督:すみません。今日ちょっと、僕ら3人だけが登壇しているんですけど、色々な方が今回来てるので。まず、本当に皆さん、映画を支えてくれたスタッフの皆さんが、今回初めて映画を観たということで、ちょっと、立っていただいてもいいですかね。
スタッフの方です。アルバイト役で3人と一緒にいた1人いた男の子。アルバイト役のチャン・ヒュー・フィンくんも来ております。
矢田部SP:手を振っていただけますか。ありがとうございます。
監督:漁師役で出演してくれた、アソシエイトプロデューサー兼出演で、前も出てもらった、來河さん、來河侑希さんです。
矢田部SP:來河さん、ありがとうございます。
監督:それと、この映画とは全然関係ないんですども、『僕の帰る場所』(18)っていうのが3年前の東京国際映画祭のアジアの未来部門で上映させてもらったんですけど、そこに出てた兄弟のカウン・ミャットゥくん、テッ・ミャナインくんとそのお母さんのケイン・ミャットゥさんが、今日来てるので、ぜひ大きく紹介を。
矢田部SP:ありがとうございます。こういった素晴らしい皆様に支えられて出来た作品ということで、本当にありがとうございます。