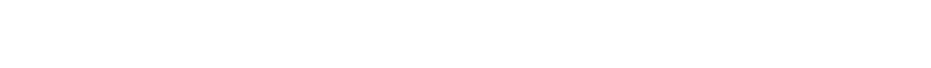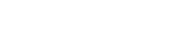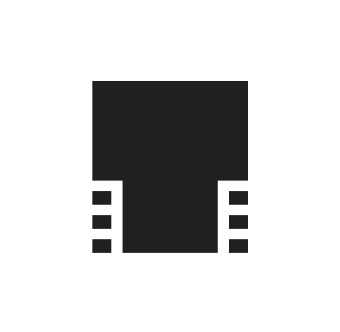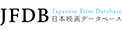11/7(日) TOKYOプレミア2020部門『私をくいとめて』上映後、大九明子監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
矢田部吉彦SP(以下、矢田部SP):これから監督をお迎えしましてQ&Aを行って参りたいと思います。それでは皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。大九明子監督です。
大九明子監督(以下、監督):ありがとうございます。大久明子です。本日はよろしくお願い致します。
矢田部SP:よろしくお願いします。どうぞお座りください。大久さん、また東京国際映画祭に戻って来て下さって本当にこんなに嬉しいことはありません。しかもまたこんなに楽しく心温まって、ちょっと深みも増した作品、ありがとうございます。
監督:こちらこそありがとうございます。本当にただいま、って気持ちです。
矢田部SP:嬉しいです。まずは改めまして、会場の皆さまに一言ご挨拶のお言葉をいただけますでしょうか。
監督:本日は夜遅い時間まで、しかもまだ世の中がなかなか出歩くことが困難な中で、私どもの『私をくいとめて』まで足をお運びいただきましてありがとうございました。133分という時間、皆様にとってどういう時間だったのかなと、ドキドキしておりますが、世界を旅するような気持ちというか、脳内で宇宙を旅するような。脳内の宇宙を旅するような気持になるようなそういう身近な物語でありつつ、そういうスケール感が出たらいいなということで、スタッフ、俳優一同で作った映画です。お楽しみいただけていましたら幸いです。よろしくお願いします。
矢田部SP:通常は冒頭の始まりと言いますか、作られた経緯だとかからお伺いしたいと思いますが、やはり皆さん、幸せの余韻に浸っていらっしゃると思うので大滝詠一さんの曲を選ばれた理由。これは原作に?
監督:あるんです。
矢田部SP:あるんですね、そうなんですね。大久さんはどのように大滝詠一さんの曲がこの作品に生きてくるといいますか、どう思われて実際にこれを使うというふうになったのでしょうか。
監督:小説の「私をくいとめて」には大滝詠一さんの歌がいっぱい出てくるんですけれども、その中でこの「君は天然色」という曲が“みつ子”の最大級の危機にあって、パンッと救うようなかたちで出てくるんです。私は単行本として手に取り、拝読したんですけれども、そもそもは新聞の連載で行われていた小説であるにもかかわらず、歌詞がそのまま出てくるんですよ。何行か使って贅沢に。その日の朝刊を開かれて読まれた方はどういう気持ちになったろうなとか、そういうことも楽しかったし、危機の中にあってボンッと歌詞がゆっくりと出てくる感じが、私もものすごく感動しまして、この曲っていうのは映画にするにあたっては絶対に外せない大事な曲になるということで、この曲はもうありきで進めますということは最初から言っていたんですが、当然のことながら、映画の中でよそ様が大事に作られた音楽を使わせていただくということは、それなりに敬意を表し、かつ色々なものが発生するんですね。色々なものが(笑)。なもので、プロデューサーとしては「え、何曲ですか?」とか「1曲だけですね」とか「使うにしてもそれは…」っていうなかなか色々あるわけなんですが「でも一曲はとにかく使います」と。そのことで「分かりました」と動いてくださって、色々な権利の許可を求めに動いていましたら、ある日、ある時、坂口 修さんという、大滝詠一さんの楽曲の権利をいろいろやっていらっしゃるナイアガラという会社の方からメールがきました。私は「時効警察」というドラマをやった時に、坂口さんとは劇伴作家としてご一緒してるんです。
矢田部SP:劇伴というのは劇中に流れる音楽ですね。
監督:はい、劇中に流れる音楽ですね。それをなさる方としてご一緒していて、その坂口さんから久しぶりに連絡がきたから何かなと思ったら「大久さん、うちの楽曲をお使いになりたいということだそうで、大大大歓迎です」みたいなメールがきて「えー!」ってびっくりして、「つきましては僕がやれる限りのことはやります」ということで、すごく色々ご尽力いただきまして、気持ちよく使わせていただいた上に、映画というのは5.1ch、音がそういう状態で聞けるようにして完成させているんですが、もともとの楽曲がそうではないので、それを5.1にするっていう作業をするには、もう一度完全に出来上がった楽曲を分解するというか、そういう作業が発生するのです。大滝詠一さんはご存知の通りすでに亡くなられておられますが、大滝さんは映画が大変大好きな方で映画に何か関わる時は必ず一つプレゼントをするというのがポリシーとしておありだったそうなのです。だから「生前の大滝の意思を鑑みて、この5.1chにするという仕事はこちらでさせていただきます」ということで、プレゼントしてくださったというか。なので、うちの整音チーム、小宮 元さんと坂口さんとソニーの整音チームとで一緒になって作っていったという経緯がございます。長くなりました、すみません。
矢田部SP:楽曲の話が出たので、歌詞が出てくるあのイメージがどのようにして監督の発想として出てきたのか、お伺いできますか。
監督:最初に小説を読んだ時から、すごく色にあふれた小説だな、というのがあって、その思いで楽しく読んでいたんで、あの楽曲が“みつ子”の耳に流れてくる爽やかさ、それを映像にする時にどうしようかなと考えている時に「コエカタマリンだな」って思ったんですよね。
矢田部SP:コエカタマリン?
監督:ドラえもんに「コエカタマリン」ってあるんですけど。
矢田部SP:あー!はいはい。
監督:そういうふうに可視化されたら面白いなと思って。「コエカタマリン」って、シナリオには本当に「コエカタマリンのように」って書いたんです。そういうことをCGではなく歌詞を小説のインパクト、歌詞が丸々出てくるということと同じようなインパクトとして色にあふれた文字が「コエカタマリン」として浮遊してるっていう映像を撮りたいなと思いました。
矢田部SP:なるほど。とてもびっくりして、とてもポップで素晴らしいシーンでした。
監督:ありがとうございます。
Q:のんさんが演じる主人公が不安症になるような原因だったり、プロフィールのようなものがあったと思いますが、監督とのんさんの間でどういうお話をされていたんでしょうか。
監督:実はそういう話は一切しておりませんで、こちらから何か「こうなんです」っていう説明は特にしなかったんですね。今までの過去の作品では、その人のプロフィールというか、この人はこういうことでこうで、みたいな散文みたいなことですね、そういったものを書いて俳優に渡すということをしてきてるんですけれども、今回はあえてしませんでした。私自身も“みつ子”という人が何か直接的な理由があって、ああいうふうになった人ではないような気がしていまして、劇中で描いている通り、一回恋愛に行動しそうになって、ちょっとショックを受けて、消極的になっているということは一つ描いてはいますけれど、具体的な何かがあって、あのようになった人ではないと私は解釈していまして。一言で言っちゃうと、どこにでもいる人だと思いたいんです。脳内に人を一人用意して、しゃべってるというのはだいぶ変わった人ではあるけれど、色々なストレスや経験値を重ねていくことで、30歳を越えて、そういった生きづらさみたいなものを感じたことがない人なんていないと思うので。それぞれに衝撃的な何か出来事があったからそうなってるとかではなく、少しずつ何かをあきらめながら大人になって、だけどまた違う視点が開いてとか。そういったどこにでもいる普通の女性であってほしかったので、今回はプロフィールを渡さなかったんです。
矢田部SP:脳内のAが女性の声でもありうるということは考えたことはありますか。
監督:それは全く考えなかったんですが、今回よくそのような質問を頂戴しまして。当たり前のように、小説が面白かったからだと思うんです。私は小説を読んでいてすごく紳士的な声で礼儀正しくしゃべるというようなことが面白く感じたので。“みつ子”がすごく、一番安心して喋ることができる喋り方をする男の人の声っていうことなんだろうなと。面白がってしまった部分があります。先日、原作者の綿矢りささんにお話聞きましたところ、綿矢さんの脳内に本当にいるらしくて(笑)。Aとは呼んでいないみたいですけど。それは男の人らしいです、やっぱり。
Q:今回キャスティングするにあたって、すぐ決まっていったのか、時間をかけられたのか、そのあたりを教えていただければと思います。
監督:キャスティングは、本を書いているときは、浮かんでいたのは前野朋哉くんだけで(笑)というか、もう小説読んでる時から絶対、もち肌というト書きがあったかな。ト書きというか、小説の中の文体で「もう日本には前野朋哉しかいない」って思って楽しく読んでたので…あの方とは何本かご一緒していて、脱がせたことなかったんですけど、確信があったんですよね。ああいう体だっていう自信があって。でもああ見えて、脱いだらガリガリだったらどうしようとか思ったんですけど、衣装合わせの日、脱いだ時もすごい自慢げに「ほら見ろ!」って「ほらこの体!」とかみんなに言っちゃいました。あとは本当にどなたにやっていただければいいのか全く浮かばなくて、困ったなと思っていたらプロデューサーが、すごく冴えていまして、ピンポイントで言ってきた人たちなんですね。「のんさんどうですか」「林遣都さんどうですか」「あ、林くんは前からやりたいと思ってました」と。なんかね、冴えてるんです、そのプロデューサー。
Q:「人間、生き物として可愛いのんさんと林遣都さんなので」っていう話の監督インタビューを拝見したんですけれども、かわいくした経緯とか、生き物としてかわいい二人のエピソードとかいただけたら嬉しいです。
監督:はい。まず、林(遣都)くんに演じて頂いた“多田くん”っていう役が、小説はもう少しがっしりしたタイプとして出てくるんですけど、主人公の“みつ子”の像を捉えにいった時に、“みつ子”が、“A”の声もそうですけど、“みつ子”がどのような人に心を許すかなぁ、あるいは、どのような人に心を閉ざすかなぁと思った時に、“多田くん”っていう人が、あのような脅かさない人、“みつ子”を脅かさない人というかたちで、シナリオを書いていくうちにどんどんどんどん“みつ子”を中心にできあがってきたキャラクターでした。小説は面白く読んでいて、別にそれを否定するつもりであのようにキャラクターを変えたというよりは、自ずとそうなっていったと。綿矢さんのものを映画化させていただくのは、これで2本目ですが、どちらも綿矢さんの小説の中では、もうちょっといかついんですよ。だから、それぞれの好みが出ているのかな?綿矢さんにそこは聞いたことないですけど、そういうところもあるかもしれないですね。そして、二人の可愛いエピソード…本番終わると喋っている様子は全くなく(笑)。誰とも特に喋らない二人なので、なんか、そわそわしていますね。ガシン!ドシン!という人たちじゃなくて、「あ、すみません。あ、すみません」っていう感じの。で、そわそわしてて(笑)。だから、映画の役がそういう感じだからそのようにしてらっしゃるのか、本当にそうなのかはよくわからないです(笑)。
矢田部SP:二人の関係を構築するために、何か事前に監督のほうから、撮影に入る前に少しやってほしいこととか、何かしらそういったことはあったんですか。
監督:いや、全くないです。全くなくて、初めてのんさんにお会いした時に、色んなお話したんですけれども、そのときに一つ質問されたのが、「これ私、ラブストーリーとして、大丈夫でしょうか」みたいなニュアンスの質問をされたんですね。その時、私が目にしていなかった、俳優へのプレゼン用の企画書があって、それを目にしたのんさんが、少し「ラブストーリー、ラブストーリーって言ってますけど、そういう感じでしたっけ、シナリオは」ってお思いになったみたいなので。多分、その企画書を私は見てないけれど、大丈夫ですよと。もちろんラブストーリーの面もあります、と。“みつ子”という、31歳になって、30代のぬるま湯に片足突っ込んでいる“みつ子”さんが、久しぶりにちょっと異性を意識して、またちょっとどぎまぎしちゃうとか、そういった面はあるけれども、必ずしもラブストーリーということではないという説明をしましたね。“多田くん”も“皐月”も、(片桐)はいりさんにやって頂いた“澤田”も、“みつ子”という人に良い変化を与えてくれる人として登場してほしかったので、そういう中の一人として、恋愛担当みたいな“多田くん”ということかなぁと思ったので、特に二人を濃密に何かを共有させようというのは、敢えてせず、どぎまぎのまんまの二人でいいやと思っていました。
矢田部SP:“澤田さん”も、隣のオカリナから…
監督:はい。『勝手にふるえてろ』ではそうですね、はい(笑)。
矢田部SP:部長職に大出世ですね(笑)。ちょっとこれはこの映画の一つのコアな部分だと思うんですけども、印象に残るのは、温泉で少し女性が雑な扱いを受けることに対して非常に憤る場面があるんですけれども、やっぱり監督があのシーンを入れることには、相当、それなりの思いがあったのかなぁと作品観ていて思うんですけれども、その辺りをお伺いしてもよろしいですか。
監督:あのシーンは小説でも素晴らしいシーンがありまして。“みつ子”が中学生くらいの女学生が、おじさんのタレントに嫌な思いをさせられていると。旅番組か何かの収録にきていたタレントのおじさんが「お菓子ちょうだい。あーん。」とか言うと、中学生の指ごと舐めるみたいな、そういう胸糞悪いシーンを描かれていて。それはそれで、すごくそこに向ける“みつ子”の眼差しが素晴らしいんですよね。「年上の女として、年下の女の子を私は守ることができなかった。苦しいよ、“A”」っていう。そのシーンをそのままやるっていうことはどうだろうかと。そこはプロデューサーと話し合いまして。だったら何か違う、私らしい何かに変化させたものにしてみようかなぁと思って。日頃思っている、職業として、笑わせることが仕事の人たちにプラスアルファを求める。全ての女性、色々あると思うんですけど、職業として全うすればいいだけのところにプラスアルファ何かの要素を求められてしまう。それをうまくやれることが、この世の中に溶け込んでいく唯一の方法だと思っていた世代の人と、今また、“みつ子”の世代は違ってきていて。ずっとおかしいんだよなって思い続けていた私の世代とかも、今は大声でそういうことが言いやすくなったっていう。これは「100年残る映画で刻んでやるんだ」っていう思いはすごくあって。“みつ子”も泣いて喚いて演じていましたけど、書いている私も、泣いて喚いていうような気分で書いていました。セリフがもう溢れるように出てきて。「彼女の面白さが1ミリも分からない、低能野郎の癖に!」みたいな。そんな普段言えない言葉をがんがん書きながら、それでもまだまだ出てくるというか。綿矢さんの小説の素晴らしさって、そういうポンと投げられたものに、私もこういうのがあるっていう、そういうのが掻き立てられる素晴らしさがあって。すごく筆も乗ったし。“みつ子”さんをやってくれたのんさんも初対面の時に「あのシーンをうまくやりたいなと思っています」と仰ってくれたんで、あのような感じになりました。
矢田部SP:そこがラブストーリー、ラブストーリーじゃないですよ。っていうところのコアにもあるわけですよね。
監督:そうですね。そういう“みつ子”さんというか、本当にさっきも言ったように、よくいる30代の女性だと思いたいんですけど、そういう女性がどういうことを感じ、考え、っていうことをちゃんと映画に刻みたいっていうことです。
矢田部SP:やはり、皆さんも聞きたいと思うんですけど、“みつ子”と親友の橋本 愛さんとの関係を監督はこの映画の中でどのように位置づけていこうと思われましたか。
監督:はい。全ては“みつ子“を中心に物語を作っていったので、“みつ子”がどういう人と出会った時に感情が動くかなと思って、親友が違うかたちになって、と言うか、久しぶりに会った親友が妊娠していたらすごく驚くだろうなと思って、その時に“みつ子”はどういうリアクションするだろうということを、私も観てみたかったということで、妊婦という設定に小説と少し変えました。
矢田部SP:そうか、小説では妊婦ではない?
監督:そうですね。やっぱり小説はあれだけたっぷり色々書きこまれているものを、133分にぎゅっとする時に、“みつ子”という人が色々なものと出会って、変化をしていったり、何かを感じたりっていうことを表現するときに、ある程度出会う人に何か役割を担って欲しいなということで、“皐月”には妊婦という役割を担ってもらいましたね。
矢田部SP:“皐月”側にもある種の苦しみとまではいかないかもしれないけれども、やはりどこかの陰が、“みつ子”と会うことによって、少し見えてくるっていうところもありますよね。
監督:そうですね、そこに関しては、当初シナリオを書いていた時よりさらに、陰みたいなものが強くなりまして。というのも、撮影が3月中旬から4月中旬でクランクアップの予定だったんですが、ご承知の通り、世界中がコロナという災いに脅かされまして、撮影も4月の頭でピタッと中断せざるを得なくなりました。そこまでまだ“皐月”を1フレームも撮っていなかったんです。“皐月”を撮っていないまま、この映画を完成させるわけにはいかないし、“みつ子”を海外に連れていかないと、この映画は完成しないということで、「さて、どうしよう」となったんですけれども。とにかく映画というのは「素敵な嘘の塊」だから、映画の中でその場所を作ろうと。言葉を選んでいますけれど、負けず嫌いなんで、「行かれなくてさ~」とか言うのが本当に嫌で。とにかく「映画の中に作ればいいんだ、よし!」ということで、私も気分がいろいろ落ち込んでいたので、そうなると“皐月”が元のままの“皐月”ではいられないと思ったので、この映画の中の世界を、少しコロナの何かがひたひたと世界のどこかでは聞こえ始めているんだけれども、まだ“みつ子”たちのところには届いていないし、“皐月”のような、命を一つ抱えて生きている、生命に敏感になっている人だけが炭鉱のカナリアのように、危機を俊敏に察知して怯えているという、そういう世界にしました。なので、彼女にだけマスクをしてもらったということがあります。
矢田部SP:おそらく今完成している作品の中で、あの時期をリアルタイムで作品の中に入れているものはほぼないですよね。コロナ禍になってからリモートなどで撮られた作品は色々あるにしても。このようなかたちで映画の中で触れている作品としては初というくらいですね。
監督:そうですね、それは一つチャレンジとしてよかったと思いたいというか、この時期をきちんと残そうと、私も意地になったところもあったし、“みつ子”と“皐月”を当初の予定通り、この可愛らしい二人が海外の街を歩いているっていう、そういう映画も本当に素敵だったと思うけれども、今回このように“皐月”に苦しい役割を担わせて、部屋に閉じこもらせるということにしたおかげで、生まれたものも色々あるなと思っています。このような世界の状況があったから、私もスカッとしたいというか、一筋の太陽を浴びさせてあげたいというか。そのような思いもあってやりましたね。
矢田部SP:最後に監督、一言頂けますでしょうか。
監督:好きなように感想を言って頂いて構わないのですが、大事な133分という皆さんの貴重な時間を頂戴したことで、それが本当にいい時間だったら嬉しいなと、ただひたすらそれだけなんですが、“みつ子”さんの脳内の旅をお楽しみ頂けていたら嬉しいです。また、公開の時には、劇場に足を運んで頂けたら嬉しいし、その時は普通に握手したり、感想を直接聞けたり、そういう時になっていたら本当に嬉しいなと思います。本日はどうもありがとうございました。
矢田部SP:ありがとうございました。この作品『私をくいとめて』は12月18日より全国一斉公開でございます。皆様、ぜひ足をお運び頂きたいと思います。