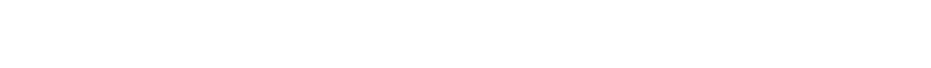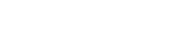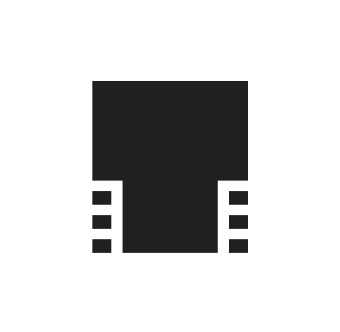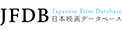東京国際映画祭公式インタビュー 2020年11月2日
『遺灰との旅』
マンゲーシュ・ジョーシー(監督/脚本)

インド・プネーに住むカルカニス一族の家長が亡くなり、「遺灰は先祖の土地とパンダルプールの川に撒くように」との遺言を残す。遺言が成就するまでは遺書の封を切ることができない。遺族たちは思惑を秘めて車で旅行する破目になる――。それぞれが事情を抱えた遺族が織りなす、コミカルなロードムービー。マラーティー語圏で活動するマンゲーシュ・ジョーシーの監督第3作は、音楽を効果的に織り込んだ皮肉の効いたファミリー・コメディだ。
――まず、どのようなアイデアからこの作品は生まれましたか?
マンゲーシュ・ジョーシー(以下、ジョーシー監督):数年前に一番上の叔父が亡くなり、亡くなった日が、年に一度のアーシャード月の11日(“ワグ”というヒンドゥー教の聖地パンダルプールを流れる川に巡礼し集まる日)の直前だったのです。遺灰を川に流しに行こうと話し合ったことから、作品のアイデアが浮かびました。
――この物語は実際の監督家族の旅なのですか。
ジョーシー監督:家族で話し合いましたが、パンダルプールは遠くて現実的ではなく、実際には行きませんでした。旅でどんなことが起こるか、想像を膨らませました。
確かに私の兄弟、叔父や叔母には映画に出てくるようなキャラクターがいます。ナイーブな兄や叔父、叔母など、実際のキャラクターに基づいていますが、ストーリー自体はフィクションです。
――インド映画には必ず音楽があり、本作も例外ではありませんね。
ジョーシー監督:最初、脚本執筆時には音楽は考えていませんでした。しかしインドは、劇場公開のときに音楽が求められるので、キャラクターに合わせた音楽を入れることにしました。音楽担当のA・V・プラフッラチャンドラと相談して、歌詞もきちんと入れました。
――配役についてはいかがですか。
ジョーシー監督:インドではよく知られた俳優にお願いしました。脚本を書いているときに既にあてがきしています。様々な映画祭で賞をいただきましたが、シニカルな作品で、ブラックユーモアがあると自覚しています。
――この映画はロードムービーで、風物や祭がすごく印象でした。
ジョーシー監督:撮影は困難の連続でした。ロケーション地域が洪水に見舞われたけれど、決行しました。幸いにも水が引いた場所があったので、長距離移動しながら撮影を続けました。
――本当に大変でしたね。
ジョーシー監督:しかも、祭には約250万人の人が一度に集まります。そのような場所に俳優を入れることができないため、その部分はVFXを駆使して後から入れました。祭り期間中は車が入れず、カメラや機材を持って3、4マイルも歩くことになりました。
――ここで監督になった経緯を教えてください。
ジョーシー監督:もともとは化学エンジニアで研究をしていました。しかし、子供の時からずっと映画製作の夢が強く、思い切って仕事を辞めました。1本目はインド政府が援助して、映画を作ることができました。ただ2本目を撮るまでに、2年を費やしました。その間に基本に戻って、映画を学び直しました。
2本目は“Lathe Joshi”という作品で、機械(Lathe)を使う労働者(Joshi)と機械そのものが、発展によって古くなってしまうという話です。この作品は高い評価を得ました。
――影響を受けた監督はいますか。
ジョーシー監督:たくさんいますが、黒澤明監督、ジャ・ジャンクー監督、ポール・トーマス・アンダーソン監督、キム・キドク監督です。特にキム・キドクの「勇敢でなければ映画は作れない」というメッセージが力をくれました。
――インドは映画産業でよく知られる国ですが、インディペンデントで製作している監督は、どのようにこの産業を見ていますか。
ジョーシー監督:ボリウッドと言われているメインストリームでは、年間1700本から1800本の作品を作っており、マラーティー語圏では年間100作くらい製作しています。同じように、10から12ぐらいの言語別の映画産業が国の中に存在しています。
私たちが作っているのはマラーティー語の映画でマハーラーシュトラ州のみの映画ですから、予算もスケールも小さく別物です。ヒンディー語でこの映画を上映するよう話し合っている最中です。
――コロナ禍の中で映画監督としてどのような思いを持たれていますか。
ジョーシー監督:今、全てがオンラインでリリースしているのに、東京はリアルで映画祭を行なっていることは素晴らしいと思います。このような状況下で、映画館に行って映画を観るのは不安ですし、これから1年くらいは避けられないかもしれません。ただ人間は、非常に社会的な生き物で、人と接したいという気持ちを常に持っていると思います。このような時期が過ぎれば、今まで以上に人と繋がりたいはずです。希望的観測ですが、このような時期がプラスの要因となると考えています。