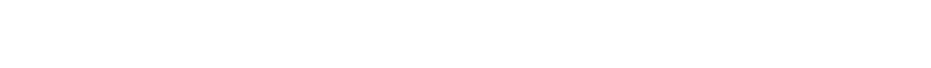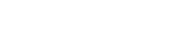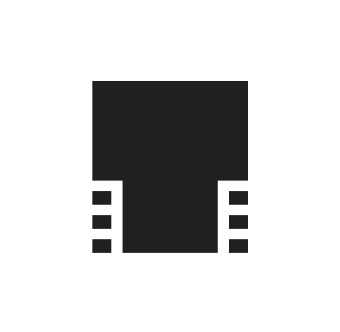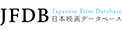モーリー・スリヤ×ヤン・ヨンヒ、女性監督として思うこと、自国を外から見るということ

モーリー・スリヤ監督(左)とヤン・ヨンヒ
第33回東京国際映画祭と国際交流基金アジアセンターによる共同トークイベント「アジア交流ラウンジ」モーリー・スリヤ×ヤン・ヨンヒ」が11月5日に開催され、ヤン・ヨンヒ監督が都内会場で、インドネシアのモーリー・スリヤ監督とオンラインで語り合った。
今回の対談をきっかけに、お互いの作品を鑑賞したというふたり。スリヤ監督の第3作『マルリナの明日』は、女性の復讐劇を描き、第18回東京フィルメックスのコンペティションで最優秀作品賞、18年インドネシア映画祭で作品賞など国内外で数々の賞を受賞した。
ヤン監督は「映画祭が育て、映画祭に発見されてはばたく監督。3作でステップアップされているのがくっきり見えて痛快でした。とてもオリジナリティの強い作品。私はインドネシアのことをよく知らないので、エキゾチックな感じがしましたし、音楽、キャラクター、そして誉め言葉としてセリフなしでも十分楽しめる映像。シーンシーンが物語っている」とスリヤ監督に感想を告げる。
ヒロインが強盗のレイプ犯を斬首し、生首を証拠として警察署まで運ぶという過激な描写があるが、「勇ましい。つらい体験をした女性が思い悩む映画は多くありますが、この映画は、絶対に負けないと果敢に立ち向かう。クズみたいなひどい男ばかりが出てくるけれど、シリアスなシーンなのに笑える。西部劇のようで、B級をアートに昇華させている塩梅が素晴らしい。女性に強烈な個性があり、インドネシアが舞台だけれど究極に普遍的」と絶賛した。
「誉め言葉が映画を作り続けるモチベーションになってうれしい」と喜ぶスリヤ監督は、在日コリアン2世のヤン・ヨンヒ監督が、自らの体験を題材に、国家の分断によって離れ離れになった家族がたくましく生きていく姿を描いた『かぞくのくに』を鑑賞し、「素晴らしくエモーショナルな映画。在日コリアンや北朝鮮のことを知らなかったので、もっと知りたいと思いましたし、物語のリアルさに引き込まれました。人間関係の葛藤や物語も共感を感じる内容。映画でご自身の人生を表現していることが素晴らしい」と感激していた。
そしてスリヤ監督は、劇映画のほか、ドキュメンタリー、小説も発表しているヤン監督に、それぞれの制作過程での違いについて質問。ヤン監督は「本は一人でできるので、とても自由。SFでも時代ものだろうが、お金がかからないので、これ以上の自由はないと思った。私は2本ドキュメンタリーを作ってから『かぞくのくに』を低予算で、2週間で撮りました。ドキュメンタリーで私は(被写体に)一度も指示したことがないんです。お願いした瞬間に信頼関係が崩れる気がして。私生活にカメラを持ち込むという厚かましいことをしているから、それを守ってきました。ですから、フィクションを撮った初日に、私が「こっちがいいな」とポロっと出た一言で、スタッフが動いたことに、ドキドキして、それを悟られないように、威厳があるように監督らしくしていろと自分に言い聞かせていました」と実体験を振り返り、「ドキュメンタリーは撮り終わって、編集しながらシナリオを作っている感じで、撮れた画でしかシナリオが描けないという難しさがある。(被写体の)一番深い話はカメラを置いた時に話してくれるので、こういう場合はフィクションの方がいいのかなと思ったり。だから、フィクションを突き詰めると真実になる。一方で、ドキュメンタリーは自分でどんどん編集して作りこむので、創作になっていく気がする」と回答した。
それぞれの国と女性監督の立場を問われると、「インドネシアには多くの女性監督やプロデューサーがいます。2000年代前半から作品が作られるようになったので、映画産業の歴史が浅いからでしょう。コロナ以前に作られた約200本の映画の半分以上が女性監督の作品です。しかし、予算が大きい映画は、経験を積んだ女性監督ではなく、若い男性監督に行くことはあります。私自身、女性監督という意識はありませんでしたが、取材で“女性監督”として質問され、初めて意識しました」とスリヤ監督。
さらに、「『マルリナの明日』は男性が考えた話なのですが、女性の視点を入れたいとのことで、私にアイデアをくれたんです。そのときは自分が女性でよかったと思いました。インドネシアは家父長制が強い国で、女性は父や兄に従い、意見しないように育てられるのが問題だと思います。女性と男性は違う感性を持っているので、もっと女性監督は増えてほしいですし、社会が女性の視点を取り入れるべき」と強く語った。
ヤン監督は「私の場合、女性だからやりやすい、やりにくいではなく、自分のバックグラウンドを話にしているので、在日コリアンや帰国事業などきちんと知られていない問題がたくさんあって、それを一から説明しなくてはならないのがしんどい。作品で評価されれば、もっと作りやすくなると思う。在日や脱北者というカテゴリーを取っ払いたい」といい、「日本でも女性監督が多く活躍していますが、今は過渡期。監督だけではなく、カメラマン、照明など、映画産業の現場にもっと女性がいてもいいと思う」と自身の考えを述べた。
また、ふたりの共通点として、外国で映画を学んだという背景がある。ニューヨークで6年間映画の勉強をしたヤン監督は「○○人だからということや、生まれ育ったところで仕事をしなければならないという感覚がない。外から、自分が生まれたコミュニティを見るという視点を持てる。日本に帰ってきた理由は、第一言語で仕事をしたかったからですが、どこの国でも仕事ができるくらいの感覚でいたい」と振り返る。
オーストラリアで6年半学んだというスリヤ監督は「私は海外に出て変わりました。1998年までインドネシアは独裁政治が敷かれていて、小中学校時代はいつも国家を歌ったり、みんな同じ絵を描いたりと、自由な思考を持つことを抑圧されていた。19歳から25歳の間に留学し、考え方が変わって再形成されたので、インドネシアの古い友人と付き合うのが難しくなった。オーストラリアに行って、目からうろこが落ちるような発見があった」と告白。
そのエピソードを受け、ヤン監督は自身の朝鮮学校時代のエピソードを挙げ「北朝鮮を祖国として、指導者を絶対化、神格化しなくてはならなかった。私はだんだん反抗的になって、悶々としていました。ニュヨークに行ったら、(そういう自分が)変わらなくていいとわかった。クリティカルシンキングを養うというか、自分の国の欠点を探せ、というような授業もあり、とても楽しかった」とスリヤ監督の経験との共通点を見出していた。
今回、初対面でのトークであったが、意気投合したふたりは「真実の作品を作られている、正直な方だと思います。お互いの魂に触れたような感じがしました。いつか実際にお会いしてお話ししたいです」(スリヤ)、「何があっても必ずお会いしましょう」(ヤン)と笑顔で手を振りながら、再会を約束していた。
新着ニュース