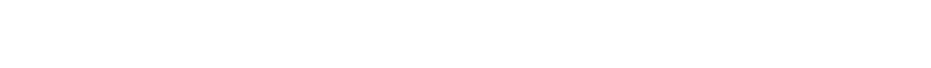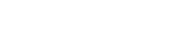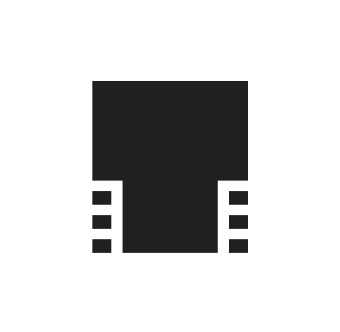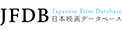シンポジウム「コロナ禍を経てこれからの映画製作」で“作り続けていくしかない”と声を揃える

(右から)登壇した紀伊プロデューサー、清水監督、福島プロデューサーら
第33回東京国際映画祭共催・提携企画である第17回文化庁映画週間のシンポジウム「コロナ禍を経てこれからの映画製作」が11月5日、東京・六本木アカデミーヒルズで開催され、『呪怨』などの清水崇監督、映画プロデューサーの紀伊宗之氏、福島大輔氏らがコロナ禍での映画製作の実体験をもとに語った。
未だに世界中に被害を及ぼしている新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、日本の映画界も多くの作品が公開延期や製作中断を余儀なくされた。しかし、そんな厳しい状況を経て、映画製作者たちは感染予防対策を講じ、映画を作り続けている。
第1部には、今年2月に公開され大ヒットしたホラー映画『犬鳴村』で組んだ清水監督と東映の紀伊氏が登壇。6月から7月に挑んだシリーズ第2弾『樹海村』の撮影などについて語った。清水監督は「スタッフからは「本当に撮影できるのか?」と問い詰められることもあったが、感染しないでできるのかは誰にも答えが出せない状況。でも、紀伊さんができる限りの感染予防対策を講じて「やる」というスタンスをとり続けてくれた」と振り返る。紀伊氏は独自のガイドライン、対策マニュアルを作成し、事前にリモートで説明会も実施。可能な限りスタッフ、キャストの不安を取り除く体制を整え、製作委員会や会社の承認を得る。さらに毎朝の検温や現場での消毒などを専門に行う“衛生班”も別に設置したという。
それでもいざ臨んだ撮影は、「キャストはフェイスガードをした状態でのテストやソーシャルディスタンスを意識しながらの現場に慣れるのに1週間くらいかかった」と清水監督。「絶対に感染しないという保証もない状況で、夏の猛暑の中、ホラー映画を作る意味があるのか自問しながら取り組んでいた」と監督としての苦悩を語った。
第2部には、来年1月に森ガキ侑大監督の『さんかく窓の外側は夜』が公開される松竹の福島氏が登壇。今年6月から7月に仙台で撮影した瀬々敬久監督の『護られなかった者たちへ』について語り、せんだい・宮城フィルムコミッションの渡邊由香里氏もリモートで参加した。福島氏は「原作の舞台設定が仙台だったので、仙台で撮影しようと準備していた。渡邊さんに間に入ってもらったことで一緒に進められた」と振り返る。
しかし、平常時であれば全面支援のスタンスであるフィルムコミッションも、コロナ禍で撮影隊を受け入れることに複雑な思いもあったようだ。「6月の段階で自粛が続く状況で、対応方針が各市町村で異なるので調整が大変だった。でも、ロケを受け入れるにあたって守ってもらいたいこと、最大限の対策を行うことで説得できた」と渡邊。「撮影できないという相談もあったが、それでも地元の方々が立ち上がってくれ、会社の決断にも助けられた」と福島氏。撮影現場でも状況に合わせて脚本変更、撮影日数減、キャスティング変更をし、エキストラも人数を減らして県外からは募集しないなど工夫しながら撮影していったという。これからの映画製作については、「予算とスケジュールを十分に確保すること。コロナ禍が続く中でもどういう風に面白いものを作っていくか、継続していけるかを考え、積極的に映画は作り続けていく」とした。
紀伊氏も「作り続けるしかない。どんな環境であっても、世界の人に見てもらうにはどうすればいいのかを考え、きっと待ってくれている人がいると信じて作っていくしかない」と先を見据える。そして、清水監督は「いま映画やドラマでは、現実とは違う世界が描かれていることに違和感を覚えている。そんな時、低予算だが、実際のコロナ禍の世界を描いた映画を見て、凄く地続きな感じがした。これこそが現実だというものを見せつけられたようで、コロナと付き合いながら生きていくしかない。でも、人間同士の触れ合い、熱量をいかに映像に収めるかが仕事。このような状況でどう表現できるのか探り探りやっていく」と思いを述べた。
新着ニュース