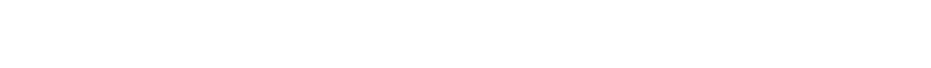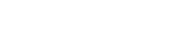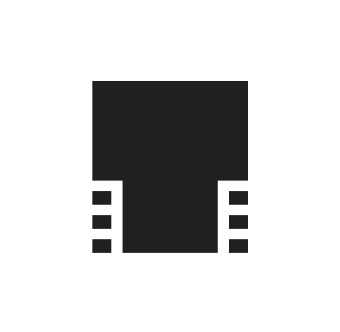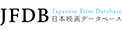東京国際映画祭公式インタビュー 2020年11月4日
『ティティ』
アイダ・パナハンデ(監督/脚本)

病院で清掃人として働く傍ら、代理母となって不妊夫婦の出産を請け負っているティティ。ロマ出身の彼女は脳腫瘍で入院してきた物理学者と出会い、人間的に共感するが…。『NAHID(ナヒード)』(16)『二階堂家物語』(18)で知られるパナハンデ監督の長編第5作は、出自の違う男女の愛の物語。主人公の無垢な人物像が笑いを誘うなか、次第にその境遇が明らかになり、恋愛と出産にまつわる重い決断が告げられる。新境地となる寓意のある作品を手がけた監督にリモートで話を伺った。
──監督はこれまで法や伝統に縛られた女性を描いてきましたが、今回は出自の違う男女の出会いを描いています。
アイダ・パナハンデ監督(以下、パナハンデ監督):主人公を代理母にしてこれまで通り女性の人権の問題を扱っていますが、本作では、異なる文化背景を持つ男女が愛を育むことは可能なのかという問題をテーマにしています。人間の孤独、突き詰めれば愛の不可能性に迫りたかったのです。
――ティティの可愛らしい無垢な性格に魅せられました。彼女は人々の救済を願い、子供のような絵を描きます。
パナハンデ監督:ティティは魅力溢れる特別な女性にしたかったので、キャラクターの推敲には物凄く時間がかかりました。私が映画史上いちばん好きな登場人物はフェデリコ・フェリーニ監督の『道』(54)のジェルソミーナで、彼女に近いイメージ──孤独だけど自由な性格にしたくて…。
ジェルソミーナのようでありながら、気高さもあるというところの線引きが難しくて、共同脚本の(アルサラミン・)アミリ(取材者注─監督の夫で編集も担当している)とは、それこそ何か月も彼女の人物造型に費やしました。
――確かに『道』の影響を感じました。ティティの人物像だけでなく、物語や三輪自動車が登場するところも。
パナハンデ監督:フェリーニ監督の影響が強く感じられるのは当然です。私はもうすぐ40歳になりますが、この歳になると、昔観た作品でも違った部分に興味を持つことが往々にしてあって、最近、特に心惹かれてきたのがフェリーニ監督だったからです。
もともと大好きな監督でしたが彼のすべての作品を見直して、今になって、神秘的な世界にいるようなマジカルな部分に感動しています。
――ティティが神秘的な能力を持っているのも、フェリーニ的でマジカルです。
パナハンデ監督:イラン映画が社会派の作品ばかりなのに私たちはうんざりしていて、せめて自分たちが作る映画はそうじゃないものにしたい。それで、神秘的な傾向を彼女に持たせることにしたんです。ずっと好きな世界だったので、これからも神秘を映画に取り入れていきたいです。
――お好きな日本映画は?
パナハンデ監督:『雨月物語』(53)と『西鶴一代女』(52)、それから『怪談』(65)です。昔の日本の映画監督たちは、寓話や神話の世界を単純に自分たちの作品に入れ込む術を知っていて、私はその作風に感動してきました。
わけても溝口健二、小林正樹、小津安二郎、黒澤明といった黄金時代の日本映画の監督たちは大好きです。イランにも寓話や神話がたくさんあるので、そうした世界に自分でも本格的に挑戦してみたいと思います。
――物理学者とミュージシャンという、好対照なふたりの男性が登場してティティの感情を左右しますが、彼らの身勝手さは溝口が映画で描いてきた物じゃないかと思いました。
パナハンデ監督:まさにその通りです(笑)。これを言うと気を悪くするかもしれませんが、アジアの国はどこも男社会であり、男たちは身勝手です。『二階堂家物語』を撮るために日本に行った時も、これだけ発展した国でさえそうした文化習慣が残っていることに吃驚しました。
イランや日本の文化に男性中心主義は深く根を降ろしていて、将来も治りそうにない。
でも、そのことを非難したくて本作を作った訳ではなく、これはある種の愛を語りたくて作った作品です。男と女の間には溝がある。それは文化であったり階級差であったりしますが、普遍性があって乗り越えられない。それこそが伝えたかったことです。
――最後のティティの告白は涙を誘います。
パナハンデ監督:ティティはすべてを失う代わりに大きな教訓を得ます。それは「知識」です。これはヴァージニア・ウルフの言葉ですが、素晴らしい物語を書く女性には、自分だけの部屋が必要になる。
物理学者とティティの恋の行方はこれからご覧になる方もいらっしゃるのでここで語れませんが、彼は知らぬ間にひとつの教訓を彼女に授けます。子供も超能力も男性も貴方の役に立たない。自立するには自分の家を作るしかないことを。
――『二階堂家物語』の加藤雅也さんは監督から厳しい駄目出しをもらい、演技観が変わったと仰っていましたが、本作でも厳しい指導をされたのですか。
パナハンデ監督:加藤さんは大変素晴らしい役者で、一緒に仕事ができて幸せでした。私よりも年上ですが、お願いしたことを非常によく理解して演じてくれたんです。彼に限らず、私の映画に出演してくれた日本の役者さんは、皆とても素晴らしかった。なぜか、私は厳しい監督だという噂が日本で流れているみたいで、誰が言い出したのかわからないんですが(笑)。
私たち映画を作る人間はスタッフを含めて、皆一丸となって作品を完成させなければなりませんが、その鍵を握っているのは役者だと、私は常々話しています。役者こそが映画の魂であって、彼らの身振り手振りを通してしか私の言いたいことは伝わらない。だから、彼らをいちばん大切に扱わなければなりません。
本作で主要人物を演じてくれた3人──エルナズ・シャケルデューストさん(ティティ役)、パルサ・ピルーズファルさん(物理学者役。TOKYOプレミア2020で上映されるもう1本のイラン映画『ノー・チョイス』にも出演)、ホウタン・シャキバさん(婚約者役)はいずれも大ベテランであり、スーパースターと呼んでいい方々ですが、幸いにも皆それぞれの役を気に入ってくれて、入魂の演技を披露してくれました。教授役のパルサさんは自身でも舞台演出を手がけている大家ですが、一生懸命に私と心をひとつにしてくれました。