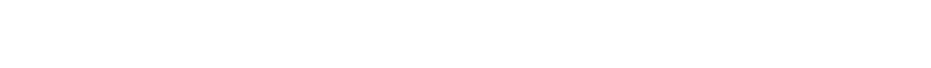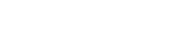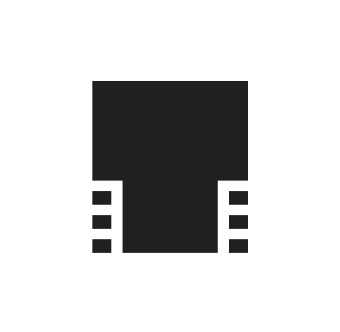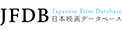コロンビアで新作撮影のアピチャッポンに空族が迫る 異国で映画を撮ること、生活の中の仏教

空族の富田克也・相澤虎之助がアピチャッポン・ウィーラセタクンと語り合った
©2020 TIFF
©2020 TIFF
第33回東京国際映画祭と国際交流基金アジアセンターによる共同トークイベント「「アジア交流ラウンジ」アピチャッポン・ウィーラセタクン×富田克也・相澤虎之助」が11月3日に開催され、空族の富田克也・相澤虎之助が都内会場で、タイの映画監督であり、アーティストのアピチャッポン・ウィーラセタクンとオンラインで語り合った。
タイを含む東南アジアが舞台の空族の『バンコクナイツ』(16)撮影前に、富田がアピチャッポンにアドバイスを求めたことから交流が始まったそうで、本イベント中もピージョー(アピチャッポン)、トミー(富田)、トラ(相澤)という愛称で互いを呼び合った。
コロンビアで撮った最新作『Memoria(原題)』の仕上げのため、バンコクのスタジオから参加したアピチャッポンは、「これからメキシコのラボに映画を送るところです。長い時間この作品に取り組んでいたので、仕上がってうれしい。ぜひ日本のお客さんに映画を見てほしい」と完成を報告。
「僕たちも南米に思いを馳せていたので、ピージョーが、何か思いがあって南米に行ったのか、そこを聞いてみたい。タイトルだけでめちゃくちゃ楽しみ」という富田の反応に「“記憶”というタイトルではあるのですが、コロンビアでメモリアというと、暴力に満ちた過去と結びつけられるのです。軍事衝突で政権で不安定だった時代です」と話し、「文明と歴史に魅力を感じていました。もちろんとアマゾンやジャングルにも。でも、今回は街にしか行っていません。もともと何か計画があったわけではありませんでしたが、目が開かれるような経験、新たな視点を持ちました」と述懐する。
さらに、異国で映画を撮ることについて、「私はコロンビアの人間ではないので、そこの状況をすべて把握できるわけではなく、あくまで部外者の目線。コロンビアの天候や建築、聞こえてくる音など自分の経験と私の印象で描きます。隠されている暴力の歴史は山の中でも街中にも感じましたが、映画ではそれは描かず、抽象的な表現を用いています。映画は作ったあとに印象が変わる。成長するように、映画の持つ人格が変化していくのです。ですから、外国で映画を撮るのは、厄介な点があります。そこの土地独自の文化、物語、記憶があるので、(外国人として)できる表現には限りがあって、表面をなぞるだけになってしまうかもしれない。きちんとわかっている人に助言をもらうのがいいと思います。私も現地の人にコンサルティングをしてもらいました」と、今回の経験を踏まえた持論を展開。
英国人女優ティルダ・スウィントンを主演に起用しているが、「彼女がタイにいるという設定の作品も考えましたが、しっくりこなかったので互いにとって外国人という場を考え、コロンビアに赴きました。彼女はとても存在感があるので、現地で自然に見えるようにすることに時間を費やしました。お互いにそこに身を置いて、地元の文化に溶け込んで何をするかを考えました」と語った。
空族の作品にも触れ、「そういった意味で『バンコクナイツ』はタイの人が抱える不安も感じ取れる、深くリサーチを重ねた、勇敢で根性の入った映画。日本語のわからない私が見ても伝わるものがありました」と感想を述べる。そして「ある意味、奇妙な描き方ともいえるかもしれません。富田さんが捉えた世界は、地元の僕にとっては見えなかった世界です。特にバーで働く女性など。また、時間軸の捉え方が、独特でした。事実と記憶と歴史が交錯して、地元の幽霊も出てくる。とりわけ後半はタイでは見られないタイプの有機的な映画。層のように重なり合って、外国人の目から見た発見が投影されていると思います」と絶賛した。
富田は「外国人である僕らが映画を撮る時には、まず(外国という)非日常の中に身を投じることになりますが、長くいると非日常が日常になる。非日常の段階で撮ると表現をミスにしてしまうと考え、日常にしようと思って長い時間をかけています。ただ、ピージョーがおっしゃった、後半の部分は非日常的な段階で感覚的に捉えたものだったかもしれません。非日常の瞬間は長くは続きませんが、非日常だからこそ気づけるインスピレーションがあり、人間の細胞の中の記憶に触れるようなものを感知できるような気がしています」と語った。
アピチャッポンは空族の最新作『典座 TENZO』(19)についても、「これも心に触れました。日本の僧とタイの僧は違う。タイの僧侶は家族も子を持つこともできません。日本の仏教哲学にもひかれました」とコメント。それを受けた富田は、仕事でフランスを訪れた際に、現地でばったりアピチャッポンに出会った際のエピソードを挙げ「僕が偶然だなあと手を差し出したら、「ノー、これはカルマだ」とおっしゃって。冗談ではないと思った」と、敬虔な仏教国であるタイの仏教の在り方について質問する。
「仏教は今の時代に役に立つというか、孤立している時代に、内省したり、人と人が内密になり、つなぐものだと思います。仏教に基づいた生き方をしていると、様々な気づきがあります。今を生きること、意味のある生き方をすること、健康を保てているのは、私は仏教のおかげかなと思っています。『典座 TENZO』の尼僧の言葉が響きました。彼女の言葉の中にある、いろんな人生がつながり、互いに影響するという概念。それぞれの生き方に意味があって、そんな中で、私は自分の身を誰にも与えていない。だからこそ感謝を持つべきだという話を聞いて考えさせられました」とアピチャッポンは回答。
アピチャッポンの仏教観を聞いた相澤は「出会って、目が開かれる。そこが一番大切な部分だと思う。僕は脚本を書くときに、人とのつながりの中で、言葉を頂き、人との出会いの中から物語が生まれていく。そして、風土や歴史など、それは自分の目が開かれないと気づけない、そこが入り口なんだなと今思っています」と続けた。
オンライン視聴の観客から寄せられたコロナ禍の過ごし方についての質問には、「家にいて、短編をたくさん作りました。また、昆虫や食物を獲ったり、天候の変化を見たり、読書もたくさんしました。次回作にコロナ禍がどう反映されるのかが気になりますが、個人的にはポストコロナで変わることはないと思います。人間は忘れっぽいものなので。映画に対しては、大きなスクリーンで見ることの意味を考えました。配信で小さな画面を見るくらいなら、自然を観察したほうが良い。先日久しぶりに映画館に行って『花様年華』のリマスター版を見ました。とても美しく、コロナを経験したからこそ、その貴重さを感じたのかもしれません」(アピチャッポン)。山梨で頻繁に釣りに行くようになった、という富田は「自然を見直すきっかけになった。僕たちの次回作は釣り映画になるかもしれません、空族が作るので、狂った釣り映画に(笑)」とリップサービス。
今後の活動については、アピチャッポンは「フィーバー・ルーム」のパート2に当たる舞台を企画しているとのこと。「自分の育った時代と新世代との比較をしたい。考えや信条の変化や今の政治活動にも関連付けたい。映画は、知性の高い海洋生物に関わった前時代的なものがテーマ」と明かす。空族は、「次回作をやろうと言い始めた段階でコロナ禍に突入したので、無理やり書くのはやめて、この状況を注視しておくことにしました。新作は今の状況が題材になっていくと思う」と富田が説明。そこに相澤が「実はコロナ前に台湾に行っていましたが、やはりストップに。チャンスがあれば台湾のプロジェクトも続けたい」と付け加えた。
トークシリーズ「アジア交流ラウンジ」は8日まで毎日ライブ配信される。Zoomビデオウェビナー(登録無料)で視聴可。第33回東京国際映画祭は、11月9日まで開催。
新着ニュース