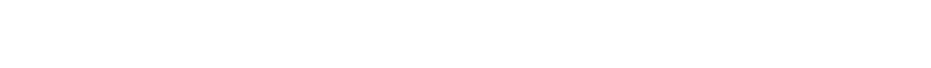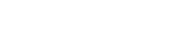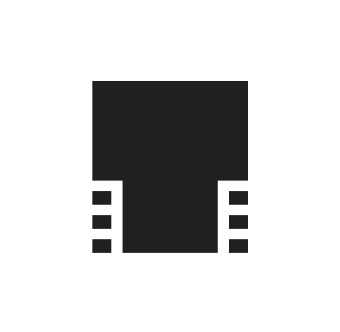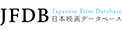アニメ監督4人が語るロケハンの効用 写実と絵の魅力のバランスが大事

アニメの美術について語った、イシグロキョウヘイ、タムラコータロー、村野佑太、佐藤順一(左から)
第33回東京国際映画祭の「ジャパニーズ・アニメーション」部門マスタークラス(シンポジウム)「2020年、アニメが描く風景」が11月7日、六本木アカデミーヒルズで開催された。同部門のプログラミング・アドバイザーを務めるアニメ評論家の藤津亮太氏による司会で、アニメ監督がアニメーションにおける美術(背景)の意義と魅力について語りあった。
登壇した監督は、イシグロキョウヘイ(『サイダーのように言葉が湧き上がる』)、タムラコータロー(『ジョゼとと虎と魚たち』)、村野佑太(『ぼくらの7日間戦争』)、佐藤順一(『魔女見習いをさがして』)の4人。各人の最新作の美術の狙いを語りながら、ロケハンや写真によって写実的な美術を描くことができることになった現状と、そこからいかに情報量を減らしたり、絵としての魅力を足したりするかの工夫を、実例を挙げながら紹介した。
佐藤監督は美術の情報量のコントロールについて、ロケハンの効用に触れながら「(ロケハン地に)愛着をもってしまうと“再現しよう”としてしまうから、その思いをとめるように心がけている」と話すと、他の監督たちも深くうなずく。また佐藤監督は、「とんがり帽子のメモル」(1984~85)で美術デザイナーを担当した土田勇氏の仕事にふれ、「僕が演出の仕事をし始めた頃は、土田さんのようなアートセンスのある方が、まず“綺麗な絵”を描いてくれた」と振り返る。そうした、絵として魅力的で表現力のある美術を描く人がいる一方、「写実的なものなら描ける」という人もいるので、より現実を取り入れるロケハンが多く行われるようになった一面があるのではと話す。
村野監督は、廃坑を物語の大きな舞台に設定した『ぼくらの7日間戦争』を制作する際、実際に取材して「想像だけでは描けないことがある」と実感し、「現地に行って実際に見ることでディテールを反映することができた」とロケハンの効果を語る。写真を美術にそのまま使うケースは少ないだろうと話し、「写真をそのまま使うと(絵としての)ハッタリがきかなくなる」と指摘した。
『ジョゼと虎と魚たち』制作のため、絵コンテ執筆前・後に舞台となる大阪を取材したタムラ監督は、友人のカメラマンに撮ってもらった写真を下敷きにした画面もあると話し、「(写真を使うと)画面の説得力が生まれるが、そこだけ情報量が高く見えてしまう」ため、写真をどう使うかのバランスが大事だと語る。イシグロ監督も「(写真を使うと)演出側からすると絵になりやすい」としながらも、写真をもとにした美術にキャラクターをのせるアニメーターへの負担と、「(写真の)ディテールをどこまで生かすかを美術監督の範疇でコントロールするのは難しい」と制作面の問題にふれた。
デジタルの恩恵で手描きでは難しかったディテールも描けるようになった一方、同じソフトを使っているため美術が画一化しがちな面もあるという話題も挙がった。「『ジョゼ』は劇場作品ということもあり、かなり手間のかかったことができた。(美術の)差別化は悩ましい問題」(タムラ監督)、「アニメの作り手側から新しいアートスタイルを提示していきたい」(イシグロ監督)、「商業ベースに縛られない、短編や個人作家から新しい美術の表現がでてくるのでは」(村野監督)、「密度の高い方向とは違うものをつくるクリエイターが出てきてほしい」(佐藤監督)と、今後のアニメ美術への展望が各監督から語られた。
第33回東京国際映画祭は、11月9日まで開催。
新着ニュース