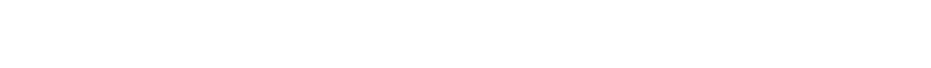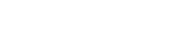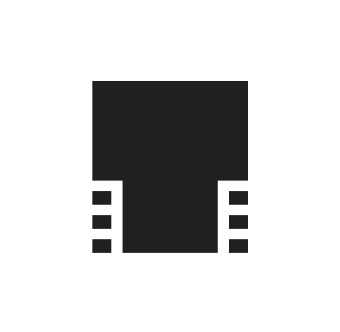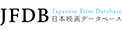藤津亮太氏に聞く、第33回東京国際映画祭「ジャパニーズ・アニメーション」部門をより楽しむためのポイント

プログラミング・アドバイザーとして企画に携わった藤津亮太氏が指南
今年の東京国際映画祭「ジャパニーズ・アニメーション」部門は、「キャラクター」をテーマにした「劇場版ポケットモンスター」シリーズ、特撮「スーパー戦隊」シリーズの足跡をたどる特集、「2020年、アニメが描く風景」を2つの柱に、新旧さまざまな作品の上映、マスタークラス(シンポジウム)が行われる。プログラミング・アドバイザーとして企画に携わったアニメ評論家の藤津亮太氏に、特集の狙いと上映作品をより楽しむためのポイントを聞いた。(取材・文/編集部)
――今年のテーマ「アニメ/特撮の描くキャラクター」の狙いについて聞かせてください。
藤津:「ジャパニーズ・アニメーション」部門は昨年からスタートして、一昨年までは監督や特定のアニメのレトロスペクティブ(※回顧上映)を中心にした内容が主でした。今年は、氷川竜介さんから引き継いで僕がプログラミング・アドバイザーをやらせていただくことになり、人間も変わるので、これを機にガラッと流れを変えつつ、もう少し振り幅を広げていけたらなと考えました。作家や映画監督という切り口での特集は、今後も必要に応じてやるべきだと思いますが、そうではない切り口も出していくことで、「日本のアニメーションが何を描いているのか」をプレゼンテーションできる“しつらえ”をつくれたらなと。その時点で今回の特集にある映画『ポケットモンスター』(※「『劇場版ポケットモンスター』の世界」)のことは頭にあって、最初にオファーをいただいた顔合わせのときから腹案として挙げていました。
――なぜ映画『ポケットモンスター』だったのでしょうか。
藤津:「ポケモン」のアニメはいま特にホットな状態なので取り上げるなら今かなというのと、日本発世界という東京国際映画祭のベクトルにもピッタリあうタイトルだと思ったんです。映画『ポケットモンスター』の歴史をたどる特集上映をすることで、ひとつの大きな柱になるなと。そこから「キャラクター」というテーマも自然とでてきました。また、「ジャパニーズ・アニメーション」部門には「VFX・特撮」という項目をいれる建付けになっていて、昨年は『ウルトラQ』の特集上映が行われました。今年は『秘密戦隊ゴレンジャー』の生誕45周年で、来年が「スーパー戦隊」シリーズ45作品目のスタート年にあたります。その流れで東映さんにご協力いただけることになり、戦隊シリーズもキャラクターという同じ枠のなかに入れることにしました。「スーパー戦隊」シリーズも「パワーレンジャー」がありますから、「ポケモン」同様、日本発世界のキャラクターという切り口が用意できます。そうした流れでこの2作品が、特集の大きな柱になりました。
――映画「ポケモン」、「スーパー戦隊」シリーズは両作品とも子ども向けタイトルでありつつ、プログラムピクチャーであるという共通点もあると思いました。
藤津:プログラムピクチャーをとりあげることを怖れないでいこうというのは最初に考えたことでした。プログラムピクチャーというか、まあ娯楽映画ですよね。映画祭ではどうしても作家という切り口が優先されがちで、それはそれで大事なことなんですけれども、日本のアニメをとらえるときにないものにされがちな娯楽映画を見つめなおすことは意味があることだと思っていました。映画「ポケモン」も「スーパー戦隊」シリーズも、ずっと続いているのには理由があって、そこには娯楽映画としていかに時代と寄り添ってきたかという歴史と、シリーズを長く続けてきた職人の工夫があります。また大きな言い方をすると、それは我々の文化や生活の一部でもあるとも思いますから、そうした視点もいれていければなと。
――なるほど。
藤津:ご存知のとおり、アニメ「ポケモン」はゲームからメディアミックスとして派生した作品ですが、劇場版をとおして見ていくだけでも監督の色や変化が感じられると思います。プログラムピクチャー的な娯楽映画って、知らない人にはアノニマス(※匿名)的に見えがちですが、映画「ポケモン」はプログラムピクチャーでありつつも「作り手がちゃんといるぞ」ということを感じやすいので、そうした点でもやる意味があるなと考えたんです。
――もうひとつのテーマ「2020年、アニメが描く風景」を設定した理由についても聞かせてください。
藤津:近年のアニメ、特に劇場アニメでは、どういうスタイルで美術を描くかが大きなテーマであり、挑戦するポイントになっていると思います。写真を参考にしたようなフォトリアルな雰囲気に仕上げることも可能ですが、リアルだけではない“絵の魅力”をどのぐらいの幅で取り戻すか。そして、それを作品の内容とどうマッチさせるかということが、いろいろなかたちで挑戦されるようになってきている印象が僕のなかにあって、「今、風景がアニメで大事である」というテーマをつくることで、上映とマスタークラスをセットでできないかと考えました。上映作品のひとつ『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は、架空の風景をリアルに描くという面白いアプローチをしています。また、「サイダーのように言葉が湧き上がる」は、風景を1980年代のイラスト風に描いているのですが、描いているのはアメリカの西海岸ではなく、ショッピングモールがある日本の田舎であるというのが面白い。『ぼくらの7日間戦争』は北海道の風景を描きつつ、旧廃坑を大きな舞台に設定していることが物語の成果にもつながっている。そんなふうに3作それぞれの特徴と狙いがあります。マスタークラスでは、特別招待作品の『ジョゼと虎と魚たち』『魔女見習いをさがして』も加えつつ、『魔女見習いをさがして』の佐藤順一監督にも登壇していただけることになっています。ベテランの佐藤監督には、時代の変化もふくめてアニメで描かれる風景の変遷についてお話をうかがえればと思っています。
――アニメの美術について考えるとき、どんなところに注目して見るとよいでしょうか。
藤津:アニメの美術は、その作品の世界観を表しています。よく言われることですが、画面を占めている面積がもっとも多いのは美術で、ふだん我々はキャラクターを注目して見ていますが、画面の印象をうけもっているのは背景の力がとても強いんです。また、さきほどお話した作り手の狙いという点でいうと、現代のアニメの美術には考えるべきパラメーターが3つあると思います。空間がきちんと描けていること、絵として魅力的であること、ある程度実景と重ねてみせられること。この3つのパラメーターを作り手がどう割り振っているかを意識しながら作品を見ると、マスタークラスの話をより楽しんでいただけると思います。
――アニメーションの画面を構成するキャラクターと美術をテーマとして設定して、セットで掘りさげていく枠組みが秀逸だなと思いました。そこも狙いとして考えられていたのでしょうか。
藤津:そこは結果としてですね(笑)。「日本のアニメーションが何を表現しているのか」を伝えるのが「ジャパニーズ・アニメーション」部門の役割だと捉えて大きな柱を設定し、これまでとは違った切り口になるようにラインナップを調整しながら反射的にカテゴライズしていったら、自然とキャラクターと美術というテーマに分離していった。そういうことだったのかなと思います。ラインナップが出そろった今思うのは、僕が何かしたというより、シンプルに面白い作品が集まったなということです。見逃した作品がある方、特別招待作品を一足先に見たい方はもちろん、どれも発見のある見応えのある作品ばかりだと思います。そして、なぜこの作品が選ばれたのだろうかと思った方は、マスタークラスを見ていただけると、より理解が深まるはずですので、あわせて気にかけていただけるとうれしいです。
新着ニュース