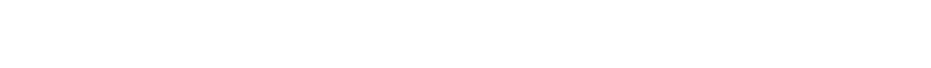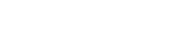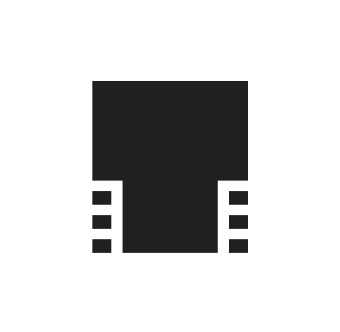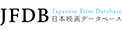深田晃司監督が説く、映画祭で最も大事なこととは?

『本気のしるし』撮影中の深田晃司監督
第33回東京国際映画祭(10月31日~11月9日)では、特集上映「Japan Now 気鋭の表現者 深田晃司」を企画し、短編含め5プログラムを上映する。2010年に手掛けた『歓待』が、第23回の同映画祭「日本映画・ある視点」部門で作品賞に輝いた深田監督が、現在まで駆け抜けた10年間を振り返った。(取材・文/編集部)
作品選定を担当した安藤絋平氏が、深田監督の魅力に迫るべく特集上映に選んだのは、第73回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションとなった最新作『本気のしるし 劇場版』、筒井真理子主演作『よこがお』、第69回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞受賞作『淵に立つ』、08年に発表した『東京人間喜劇』、短編プログラム(『move 2020』『ヤルタ会談 オンライン』『鳥(仮)』『いなべ』『ざくろ屋敷 バルザック「人間喜劇」より』というラインナップ。
『歓待』が第23回で受賞してからの10年間は、怒涛の日々だったことを明かす。
「国際映画祭で初めてもらった賞なんです。この国際映画祭で賞をいただくということが、どれだけ作品の後押しになるかということを実感することができました。これをきっかけに、多くの映画祭で上映されることになりましたから。この10年間は、長かったのか短かったのかよく分からないです。ただただ映画を作っていたという印象ですから。『歓待』のあと、6本の長編映画を作ることができました。努力や才能以上に、運が良かったと思っています」
その一方で、12年に特定非営利活動法人「独立映画鍋」を有志数人と設立。メジャーとインディペンデントの対立的な二元論に陥らない映画の多様性を創出する活動を、積極的に行ってきた。「細々と8年間活動してきましたが、日本映画を支える制度がうまくいっていないとずっと思っています。そういった問題意識が、ようやく業界内でも浸透してきているという実感はあります。日本映画の制度設計と向き合わざるをえない10年間だったと思っています」。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、多くの新作映画が公開延期となり、世界中の映画祭も中止を決断するなど運営の在り方を問われている。深田監督は、「続けることはとても大事なこと」と話す。
「映画祭はただのお祭りではなく、重要な公的役割を担っているわけです。映画祭によって、映画の多様性が支えられている面が大きいと思っています。映画祭は経済の原理主義とは異なるところで、ハリウッドの論理とは違うところで作品を評価し、後押しをしていくべき。それによって、小さいながらも市場を作っていくという貢献を、映画祭はずっと続けてきたわけです。コロナ禍になったからといって、急にいらなくなるものでもない。映画の多様性は表現の多様性であり、自由であり、社会の多様性を支えているものなので、きちんと継続していくことが大事だと思っています」
そのうえで、本映画祭にしかない強みがあることを指摘する。
「日本の映画関係者とのネットワークは、韓国にもフランスにもイタリアにもないんです。日本の映画人と繋がれる場というものは、東京にしかない。TIFCOMや映画祭のパーティが重要な役割を担っていると思います。海外から日本に来る人は、外国の映画人と知り合うためではなく、日本の映画人と知り合いたくて来日するはずなんです。そのネットワークが、この映画祭には本来あるはずなんですね。そういった交流の場は、もっと増やすべきだと思います。もしも、そこがまだ足りていないのならば、強化していかなくてはいけない部分だと思います」
そして最後に、映画祭で何が最も大事であるかを訴えた。
「シニア・プログラマーの矢田部吉彦さんら、プログラマーの皆さんがどういう作品を選んだのか、そこがすごく興味深いですし、楽しみです。映画祭は本来、土地に根差してやっていますが、本当に大事なのは土地じゃなくて人なんです。この映画祭のプログラマーが、どんな作品を選ぶのか。そこに映画の新しい価値の創造があると思います。根幹にあるのは人である、ということを見失わないでもらいたいですね。あと、いち映画ファンとして山中貞雄監督の特集は楽しみで仕方がありません」
新着ニュース